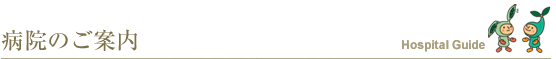��1�́@��È��S�Ǘ��Ɋւ����{
-
1�D�ړI
�{�w�j�́A�������q��ȑ�w������ÃZ���^�[�ɂ����āA��È��S�Ǘ��ɕK�v�Ȏ������߁A��Â̈��S�Ǘ��̂��߂̑̐����m�ۂ��A�ǎ��ň��S�Ȉ�Â̒Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B -
2�D��È��S�Ǘ��̊�{
�{�w�̑n���҂̒ɂ��u�����v�Ɓu���v����Ê����̐��_�I��ՂƂ��A���̐��_�̂��ƂŁu���Ғ��S�̈�Áv���s���邱�Ƃ͓��@�̎g���ł���A�ȉ��̍��ڂ���È��S�Ǘ��̊�{�Ƃ���B- �P�j�{�w�n�݂̎v�z�ł���u�����v�Ɓu���v����{�ɁA���҂̂��߂̈�Â���ш��S�Ǘ����m������B
- �Q�j���҂̗��v��D��Ƃ��A�����Ȏp���Őf�Âɂ�����B
- �R�j�Տ����C�a�@�Ƃ��āA���҂����S���Ď�f�ł�����S���Ǝ��̍�����Â����B
-
3�D�E���̐Ӗ�
�E���͋Ɩ��̐��s�ɂ�����A���҂ւ̈�ÁA�Ō쓙�̎��{�A���i�A��Ë@�퓙�̎�舵���ȂLj��S�Ȉ�Â��s���悤�אS�̒��ӂ��ƂƂ��ɁA���̂𖢑R�ɖh�����߂̒m���E�Z�p���K�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��2�́@��È��S�Ǘ��Ɋւ���ψ���Ȃ�тɑg�D�Ɋւ����{���j
-
1�D�ψ���̐ݒu
1)���@�ł̈�È��S�Ǘ��̐��̊m�ۂ���ѐ��i�̂��߂ɁA��È��S�Ǘ��ψ����ݒu����B��È��S�Ǘ��ψ���͎��Ɍf�����������̂Ƃ���B- (1)��È��S�Ǘ��ψ���̊Ǘ�����щ^�c�Ɋւ���K����߂邱�ƁB
- (2)�d�v�Ȍ������e�ɂ��āA���҂ւ̑Ή����܂ߕa�@�����֕��邱�ƁB
- (3)�d��Ȗ�肪���������ꍇ�́A���₩�ɔ����̌����͂��A���P��̗��Ă���ю��{�Ȃ�тɐE���ւ̎��m��}�邱�ƁB
- (4)��È��S�Ǘ��ψ���ŗ��Ă��ꂽ���P��̎��{��K�v�ɉ����Ē������A���������s�����ƁB
- (5)��1����x�J�Â���ƂƂ��ɁA�d��Ȗ�肪���������ꍇ�͓K�X�J�Â��邱�ƁB
- (6)�e����̈��S�Ǘ��̂��߂̐ӔC�ғ��ō\������邱�ƁB
2)��È��S�Ǘ��ψ���́A���̈�Â̈��S�Ɋւ���ψ���(�@��������ψ���A��Έψ��)�ƘA�g���A�@���S�̂̈�È��S�Ǘ��̐����m�ۂ���B
2�D���̐ݒu
���@�ɂ������È��S�̐��m�ۂ̂��߂̊������s���A�g�D���f�I�Ɉ�È��S��𐄐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA��È��S�Ǘ��҂���т��̑��K�v�ȐE���ō\�������È��S��ݒu����B��È��S�͎�Ɏ��̋Ɩ����s���B- 1)��Î��̖h�~�Ɋւ�������W�A�W�v�A���́A�����āA�t�B�[�h�o�b�N�A�]���B
- 2)��Î��̔������ɂ����锭������Ȃ�тɊ��ҁE�Ƒ����ւ̑Ή��A�֘A�����Ƃ̘A�g�E�����B�֘A�ψ���̊J�ÁB
- 3)��È��S�Ɋւ���g�D���f�I�ȉ��P��̗��āE���{�E�]���B
- 4)��È��S�Ǘ��Ɋւ���E������E���C�B
- 5)���̑���È��S�Ǘ��̐��̐��i�Ɋւ��鎖���B
3�D�Ǘ��҂̔z�u
- 1) ��È��S�Ǘ��ӔC��
��È��S�̊m�ۂ̓����ӔC�҂Ƃ��āA�a�@���͈�È��S�Ǘ��ӔC�҂�z�u���A��È��S������S�����@���������Ă��Ă�B��È��S�Ǘ��ӔC�҂́A��È��S����������A��È��S�̊m�ۂɕK�v�ȏ��̎��W����ѕ��͂�S�������ɍs�킹�A���̌��ʂɉ����ēK�ȑ[�u���u���A���{����悤�w������B - 2) �e���ӔC�҂̔z�u
�a�@���́A�e���̐ӔC�҂Ƃ��Ĉ�È��S�������A���i���S�Ǘ��ӔC�ҁA��Ë@����S�Ǘ��ӔC�ҁA��Õ��ː����S�Ǘ��ӔC�ҁA������������z�u����B
�e�ӔC�҂́A�Ώۗ̈�ɂ�������S�Ǘ��̂��߂̃}�j���A�������Ǝ��{�̓O��A�E�����C�A���S�Ɋւ�����̎��W�Ǝ��m���s���B
- (1�j���i���S�Ǘ��ӔC��
- 1�j���i���S�Ǘ��ӔC�҂́A���i�Ɋւ���\���Ȓm����L�����t�A��t�܂��͊Ō�t�̂����̂����ꂩ�̎��i��L����҂Ƃ���B
- 2) ���i���S�Ǘ��ӔC�҂́A���Ɍf����Ɩ����s�����̂Ƃ��A���i���S�Ǘ��ψ���Ȃ�тɈ�È��S�Ǘ��ψ���Ƃ̘A�g�̉��A���{�̐����m�ۂ���B
- �@ ���i�̈��S�g�p�̂��߂̋Ɩ��Ɋւ���菇���̍쐬�B
- �A ��Ï]���҂ɑ�����i�̈��S�g�p�̂��߂̌��C�̎��{�B
- �B ���i�̋Ɩ��菇���Ɋ�Â��Ɩ��̎��{�B
- �C ���i�̓K���g�p�̂��߂ɕK�v�ƂȂ���̎��W�B
- ���̑��̈��i�̓K���g�p��ړI�Ƃ������P�̂��߂̕���̎��{�B
- (2�j��Ë@����S�Ǘ��ӔC��
- 1�j�a�@�Ɉ�Ë@��̈��S�g�p�̂��߂̐ӔC�҂Ƃ��Ĉ�Ë@����S�Ǘ��ӔC�҂������B
- 2�j��Ë@����S�Ǘ��ӔC�҂́A���Ɍf����Ɩ����s�����̂Ƃ��A��Ë@����S�Ǘ��ψ���Ȃ�тɈ�È��S�Ǘ��ψ���Ƃ̘A�g�̉��A���{�̐����m�ۂ���B
- �@ ��Ï]���҂ɑ����Ë@��̈��S�g�p�̂��߂̌��C�̎��{�B
- �A ��Ë@��̕ێ�_���Ɋւ���v�揑�̍��肨��ѕێ�_���̓K�Ȏ��{�B
- �B ��Ë@��̈��S�g�p�̂��߂ɕK�v�ƂȂ���̎��W�B
- ���̑��̈�Ë@��̈��S�g�p��ړI�Ƃ������P�̂��߂̕���̎��{�B
- 3) ��Ë@����S�Ǘ��ӔC�҂�⍲���A�Ɩ����~���ɐ��i���邽�߁A��Ë@����S�Ǘ����ӔC�҂����B
- �@ ��Ë@����S�Ǘ����ӔC�҂́A��Ë@����S�Ǘ��������������Ă��Ă�B
- (3�j��Õ��ː����S�Ǘ��ӔC��
- 1�j�a�@�ɐf�×p���ː��̈��S���p�̂��߂̐ӔC�҂Ƃ��Ĉ�Õ��ː����S�Ǘ��ӔC�҂������B
- 2�j��Õ��ː����S�Ǘ��ӔC�҂́A���Ɍf����Ɩ����s�����̂Ƃ��A��Õ��ː����S�Ǘ��ψ���Ȃ�тɈ�È��S�Ǘ��ψ���Ƃ̘A�g�̉��A���{�̐����m�ۂ���B
- �@ �f�×p���ː��̈��S���p�̂��߂̎w�j�̍���B
- �A ���ː��f�Âɏ]������҂ɑ���f�×p���ː��̈��S���p�̂��߂̌��C�̎��{�B
- �B �Ǘ��E�L�^�Ώۈ�Ë@�퓙��p�������ː��f�Â���҂̓��Y���ː��ɂ�������ʂ̊Ǘ��y�ыL�^�A���̑��̐f�×p���ː��̈��S���p��ړI�Ƃ������P�̂��߂̕���̎��{�B
- �C ���ː��̉ߏ����A���̑��̕��ː��f�ÂɊւ��鎖�ᔭ�����̑Ή��B
- (4) ��È��S�Ǘ���
- 1�j��È��S�Ǘ��҂́A��t�A��t�܂��͊Ō�t�̂����̂����ꂩ�̎��i��L���A����̈�È��S�Ǘ����C���C�������҂Ƃ���B
- 2�j��È��S�Ǘ��҂́A��È��S�Ǘ��ψ���̍\�����ƂȂ��Â̈��S�Ǘ��Ɋւ���̐��̍\�z�ɎQ�悵�A��È��S�̋Ɩ��Ɋւ����旧�Ă���ѕ]���A�ψ���̊e�튈���̉~���ȉ^�c���x������B�܂��A��È��S�Ɋւ���E���ւ̋���E���C�A���̎��W�ƕ��́A��̗��āA���̔������̑Ή��A�Ĕ��h�~�����āA�����\�h����є����������̂̉e���g��̖h�~��ɓw�߂�B�����āA������ʂ��A���S�Ǘ��̐���g�D���ɍ��Â����@�\�����邱�ƂŁA���@�ɂ�������S�����̏����𑣐i����B
- 3�j��È��S�Ǘ��҂́A��È��S��̐��i�Ɋւ���Ɩ��ɐ��]�����A��È��S�Ɋւ��g�D����ъe���S�Ǘ��҂��x���E�������A�A�g���邱�Ƃɂ������̐����m�ۂ���B
- 4) ��È��S�Ǘ��҂́A�a�@����茠�����Ϗ�����A�g�D���f�I�ɋƖ��ɓ�����B
4�D�Z�[�t�e�B���N�I���e�B�}�l�W���[�̔z�u
�e����̈�È��S�Ǘ��̐��i�Ɏ����邽�߁A�Z�[�t�e�B���N�I���e�B�}�l�W���[�i�ȉ�SQM�j��z�u����B- 1)SQM�́A�f�Õ���A�Ō암��A�f�Îx������A���Ҏx������A���������炻�ꂼ��I�C����B
- 2)SQM�͎�Ɉȉ��̋Ɩ����s���B
- (1)�e����ɂ�����C���V�f���g�E�A�N�V�f���g�̔��������E�X���̕��́E���P�����A��È��S��̐��i�Ɋւ錟������ђB
- (2)��È��S�Ǘ��ψ���ɂ����Č��肵�����j�E���̖h�~��E���P�����Ɋւ��鎖���̊e����ւ̎��m�B
- (3)���̑��A��È��S�Ǘ���̐��i�Ɋւ��鎖���B
��3�́@��È��S�Ǘ��̂��߂̌��C�Ɋւ����{���j
-
1�D��È��S�Ǘ��̂��߂̐E�����C
- 1)���C�́A��ÂɊւ���S�Ǘ��̂��߂̊�{�I�l��������ы�̓I�������ɂ��ĐE�퉡�f�I�ɊJ�Â��A�X�̐E���̈��S�Ɋւ���ӎ��A���S�ɋƖ��𐋍s���邽�߂̋Z�\��`�[���̈���Ƃ��Ă̈ӎ��̌��㓙��}��ƂƂ��ɁA���@�S�̂̈�È��S�����コ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
- 2)���C�́A�N2����x����I�ɊJ�Â��鑼�A�K�v�ɉ����ĊJ�Â���B
- 3)�V�l��ÐE�Ώۂ̌��C�͕K�{�Ƃ��A���r�̗p�҂Ȃ�тɋA�ǎ҂ɂ��Ă��K�X�J�Â���B
- 4)��È��S���i�ɕK�v�Ȑ�匤�C�̊J�ÂȂ�тɊO���@���C��ւ̎Q����}��B
- 5)���C�����{�����ꍇ�A���{���e(�J�Â܂��͎�u�����A�o�ȎҁA���C���e)���L�^����B
2�D���C�ւ̎Q��
���@�̐E���͌��C�����{�����ۂɂ́A�ɗ͎�u����悤�ɓw�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
��4�́@���̕��̈�ÂɊւ����S�m�ۂ�ړI�Ƃ������P�̂��߂̕���Ɋւ����{���j
-
1�D���S�̊m�ۂ�ړI�Ƃ����̐�
���҂̈�È��S�m�ہA��Î��̖h�~�̊ϓ_����A��Â��s���ߒ��Ŕ��������z�肵�Ă��Ȃ��������ۂ�D�܂����Ȃ����ۂ̔����҂܂��͓����҂͏���̕��@�ŕ���B -
1)�Ƃ��̖ړI
���́̕A���̎��W�E���͂��s���A��Î��̂�h�~���邽�߂̉��P����쐬���A��Î��̂𖢑R�ɖh�~����V�X�e�����\�z���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B -
2)���ׂ�����
��Ís�ׂ��s���ߒ��ŁA��Î҂���̕s�K�؍s�ׂ��������ꍇ�A�s�K�łȂ��������\�z����Ă��Ȃ��s�s���Ȍ��ʂ��������ꍇ�A��Ís�ׂɊւ�����A���җv���ł̕s�s���Ȏ��ԁA�Ȃǂɂ��āA���҂ւ̉e���̗L���ɂ�����炸�A�����ꂩ�ɊY������ɑ��������ꍇ�ɕ���B -
3)�̕��@
�́A�����Ƃ��ăC���V�f���g�E�A�N�V�f���g���|�[�g�V�X�e����p���čs���A�͐f�Ø^�A�Ō�L�^���Ɋ�Â������݂̂��L�ڂ���B -
4)�҂̕ی�
�{�w�j�ɂ��������ĕ��s�����E���ɑ��A����𗝗R�Ƃ��āA�E���㓙�ɂ����ĕs���v�Ȏ�舵�����s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B -
5)���P����
�@��������ꂽ����Ȃ�тɈ�Â̈��S�Ɋւ���e����Ɋ�Â��A��È��S�Ǘ��ψ���A�@��������ψ���Ȃ�т����ψ���ƘA�g���A��Â̈��S�Ɋւ���Ĕ��h�~�����P��𗧈Ă��E���ւ̎��m��}��B�܂���È��S�Ǘ��ψ���͉��P�L���ɋ@�\���Ă��邩�����A�K�v�ɉ����Č�������}��B -
6)���̓����҂ւ̔z��
�Ǘ��ғ��́A��Î��̂Ɋւ���������҂ɑ��āA���ҁE�Ƒ��ւ̑Ή����\���Ȕz�����s���ƂƂ��ɁA���_�I�P�A�⑊�k�ɉ�����̐��̐����Ȃ�тɓ����҂̌l���ی쓙�ɏ\���z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��5�́@���҂ɏd��ȏ�Q�������������̑Ή��Ɋւ����{���j�j
-
1�D���Ґ������ŗD��
��Â��s���ߒ��ŁA���҂ɗ\�����ʏd��ȏ�Q�����������ꍇ�́A���҂̐������ŗD��Ƃ��A�㒷��t�����ɘA�����A�f�Â̎w�������A��Âɖ��S�̑̐��ŗՂށB�܂��A�֘A����X�^�b�t���Ƃ̘A�g�ɂ��A��Ã`�[���Ƃ��đΉ�����B -
2�D�L�^
�E���́A���̌o�߂���m�F���A�����o�߂���ËL�^�ɐ��m�ɋL�^����B�Ȃ��A���̂Ɋ֘A������ޥ���͌����m��̕��i�Ƃ��ĕۊǂ���B -
3�D���ҥ�Ƒ��ւ̐���
���̔�����A�f�ÂɎx����������Ȃ�����y�I���₩�ɁA���̂̓��e����ї\����A��ËL�^���Ɋ�Â������o�߂𐳊m�ɂ킩��Ղ���������B -
4�D���̂̕�
�f�ÂɎx��𗈂����Ȃ�����y�I���₩�ɁA���������̓����҂܂��̓��X�N�}�l�[�W���[����È��S��(��È��S�Ǘ���)�ɘA�������A�C���V�f���g�E�A�N�V�f���g���|�[�g�̓��͂��s���B��È��S��(��È��S�Ǘ���)�́A��È��S���S�����@���Ȃ�тɕa�@�����v�������m�ɕ���B
��6�́@��Ï]���҂Ɗ��҂Ƃ̊Ԃ̏��̋��L�Ɋւ����{���j
-
1�D���̋��L
���ؒ��J�Ȑ����������Ɩ]�ފ��҂ƁA�\���Ȑ������s�����Ƃ���Ò̏d�v�ȗv�f�ł���Ƃ̔F��������Ï]���҂��A���͂�������Ê���z�������K�v�ł���A��Ï]���ґ�����̏\���Ȑ����Ɋ�Â��āA���ґ��������E�[���E�I���E���ӂ�������悤�A��Ï]���҂͊��҂Ƃ̊Ԃŏ������L����悤�w�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B -
2�D�w�j�̉{��
�{�w�j�́A���҂���т��̉Ƒ�����{���̐\���o���������ꍇ�ɂ́A���₩�ɉ�������̂Ƃ���ƂƂ��ɁA�z�[���y�[�W���Ō��J����B
��7�́@���҂���̑��k�ւ̑Ή��Ɋւ����{���j
-
1�D���ґ��k�����̐ݒu
- 1)���҂�Ƒ�������̑��k���ɉ�������̐����m�ۂ��邽�߂̊��ґ��k�����Ƃ��āA���Ҏx���Z���^�[���S������B
- 2)���k�����s�������҂�Ƒ����ɑ��ẮA����𗝗R�Ƃ��ĕs���v�Ȏ�舵�����s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
- 3)���k�������e���ɂ��ĐE����m�蓾�����e���A�����ȗ��R�Ȃ����̑�O�҂ɏ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
- 4)���k�������e�͋L�^����ƂƂ��ɕa�@���ɕ���B�܂��A���k���ň�È��S�Ɋւ����̂ɂ��ẮA��È��S�Ǘ�����ƘA�g���đΉ����A���S��̌��������Ɋ��p����B
- 5)���k�������̒S���҂Ɩ��ڂȘA�g��}��A��È��S�����ɌW�銳�ҁE�Ƒ��̑��k�ɓK�ɉ�����̐����x�����邱�ƁB
��8�́@���̑���È��S���i�̂��߂ɕK�v�Ȋ�{���j�j
-
1�D��Î��̎���̕�
��Î��̂̔����\�h�E�Ĕ��h�~����u���邽�߂́A���̎���̕Ɋւ��鎖�����߂��A��Ö@�{�s�K����9����23��1����2���Ɏ�����Ă��鎖�ĂɊY�����鎖��ɂ��āA��È��S���珊��̋@�ւɕ���B- 1)���i�E��Ë@����S����
���i��Ë@�퓙�@��68����10��2���Ɏ�����Ă���A���i�܂��͈�Ë@��̎g�p�ɂ�镛��p�A�����ǂ܂��͕s��̔����ɂ��āA�ی��q����̊�Q�̔����܂��͊g���h�~����ϓ_����̕K�v������Ɣ��f�������(�Ǘ�)�ɂ��āA��ܕ����珊��̋@�ւɕ���B - 2)��Î��̏����W�����Ƃւ̋���
��Î��̏����W������(�X�̈�Ë@�ւ����W�E���͂�������A���Y������Ɍ���������Ȃǂ����W�E���͂��A���邱�Ƃɂ��A�L����Ë@�ւ���È��S��ɗL�p�ȏ������L����ƂƂ��ɁA�����ɑ��ď�����邱�ƂȂǂ�ʂ��āA��È��S��̈�w�̐��i��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���)�ɑ��A��È��S���玖��̕��s���B
- 1)���i�E��Ë@����S����
-
2�D�w�j�̎��m
��È��S�Ǘ��ψ���͖{�w�j��S�E���Ɏ��m�O�ꂷ��B -
3�D�w�j�̉���
�{�w�j�́A��È��S�Ǘ��ψ���ɂ����āA����I�Ȍ������Ȃ�тɈ�Ö@�̉������K�v�ɉ����ĉ������s���B