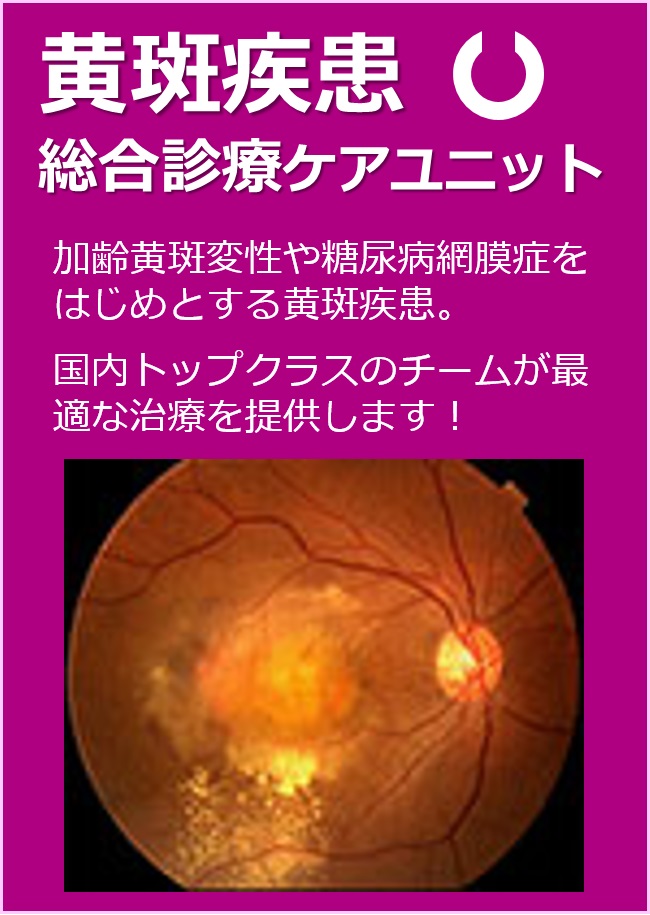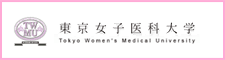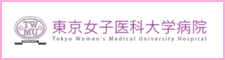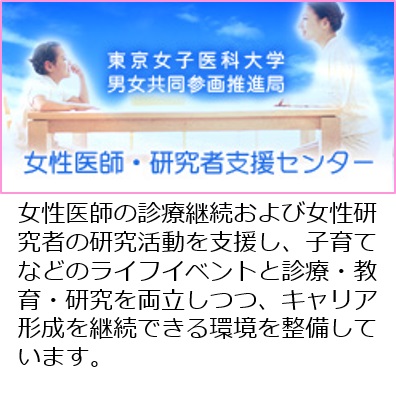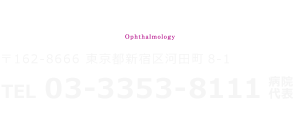当教室の女性医師支援の取り組み
本学は平成11年に制定された「男女共同参画社会基本法」の趣旨に取り組み、さまざまな女性医師の勤務継続に対する支援を行っています。当教室は入局者の8割が女性であり、過去には出産・育児で離職せざるを得なかった女性医師が多数おりました。出産は女性に恵まれた権利ですが、育児の負担により第一線から遠ざかると、再就職する機会はおよそ皆無でした。
このような状況を踏まえて、女性医師の就業を継続しうる環境や制度作りを積極的に試み、支援を行っています。実際に、育児休暇を終了した女性医師に実行している対応策は以下の通りです。
1.短時間勤務
育児期間にある女性医師およびその配偶者に、児が小学校6年生になるまでの間、育児に利用する時間を考慮した「短時間勤務制度」が東京女子医科大学全体に適応する制度として平成20年8月に発足しました。短時間勤務制度は助教以上の臨床系職員が対象です。給与は勤務時間に応じて減額されますが、身分は大学の常勤職員で、健康保険を含む社会保障制度はすべて常勤職員と同様に扱われます。 現在、3名の医局員がこの制度を利用して仕事と子育てを両立させています。
2.常勤待遇の嘱託医師雇用
勤務時間を短縮して常勤医体制の50%以上の内容で勤務してもらう体制で、主に関連病院で実施しています。対象者は育児休暇を終了後に臨床医としての職場復帰を希望するけれども、大学の常勤医としての勤務は続けられない者です。給与は常勤医のおよそ半額で、健康保険を含む社会保障制度はすべて常勤医と同様に扱われます。大学から派遣される形態をとるので、大学での職責は維持されます。
3.勤務先(関連病院)の考慮
主任教授の独自の判断による考慮で、育児休暇明けの可及的早期に、眼科当直のない関連病院に優先的に派遣されます。大学から派遣される形態なので、大学の職責は維持されます。
また、本学の『男女共同参画推進局』には、「女性医師・研究者支援センター」や「女性医師再教育センターが」などがあり、保育支援として、院内保育所(昼間保育・延長保育・夜間保育・土日保育・病児保育)が利用できます。平成20年12月から学童保育も始まり、より勤務を継続しやすい環境が整い、さまざまなニーズに柔軟に対応しています。