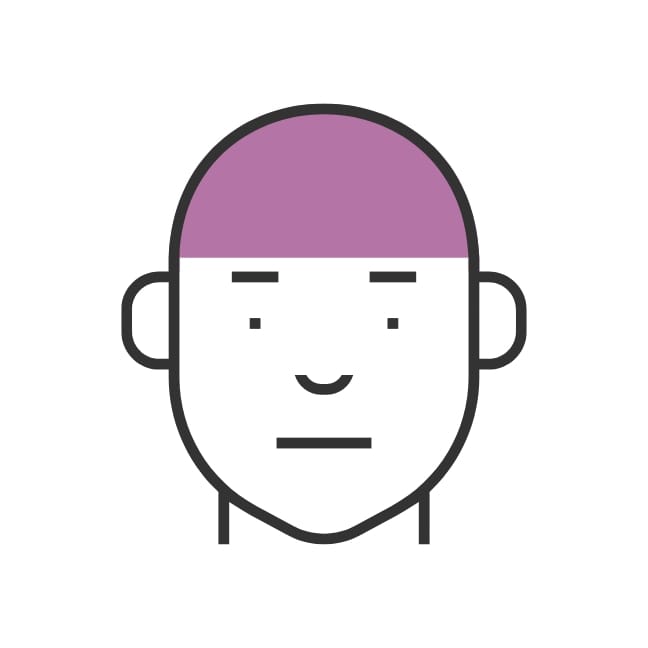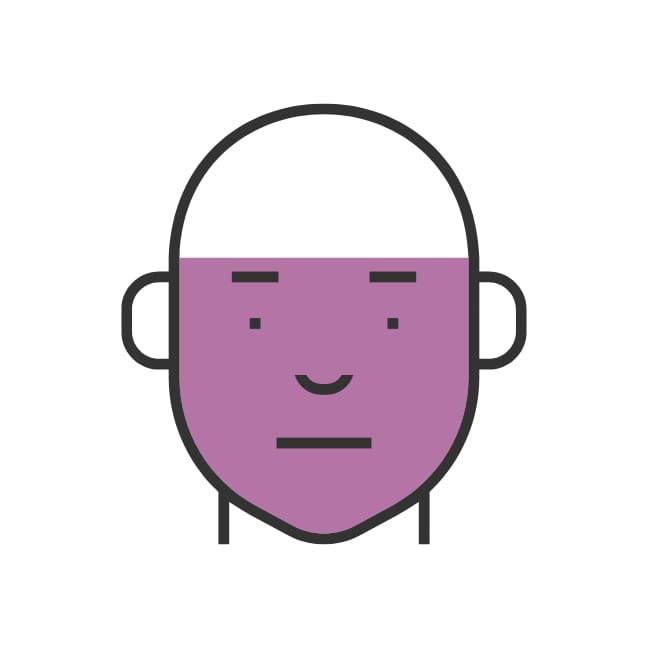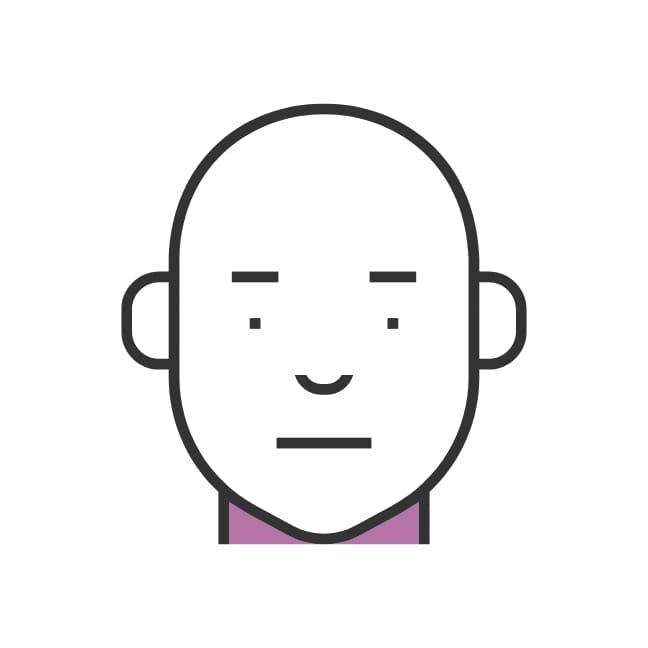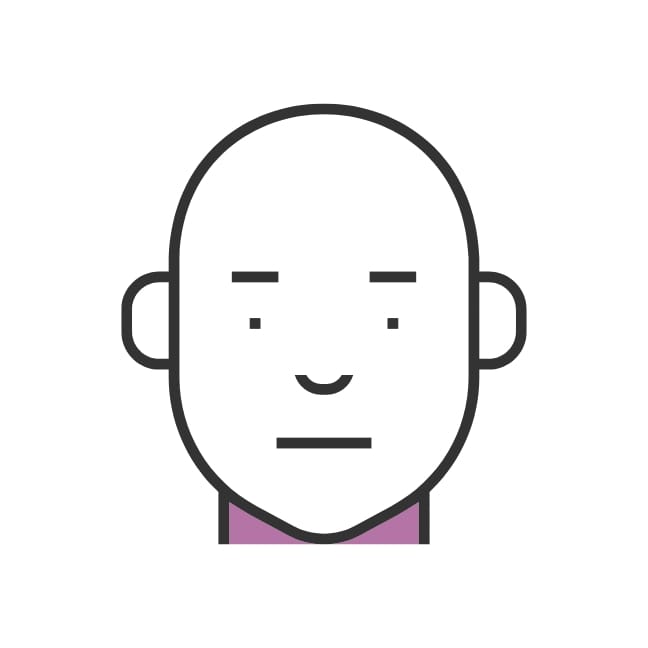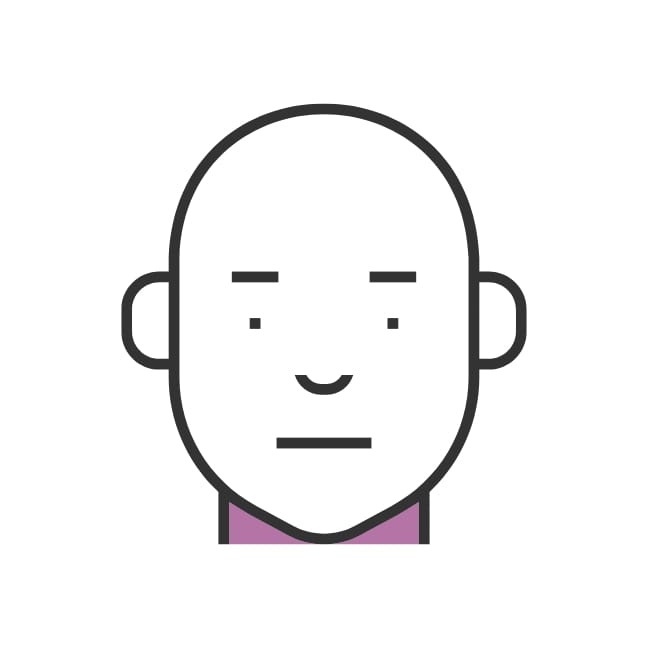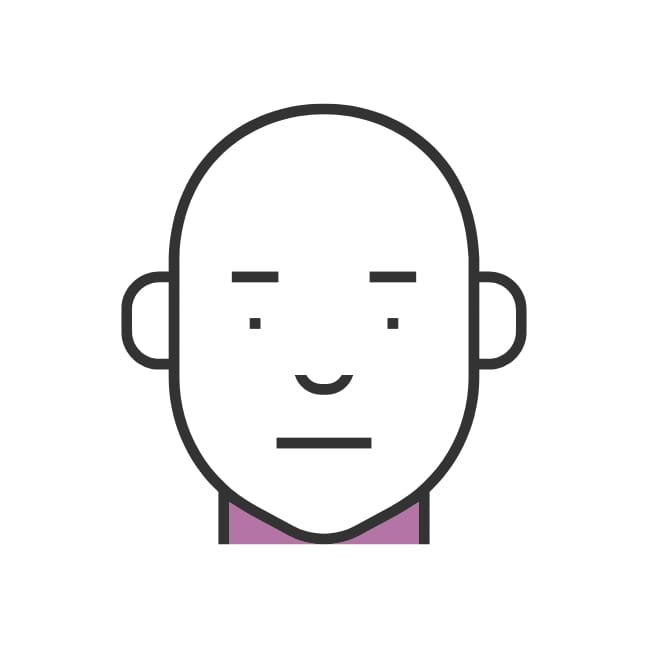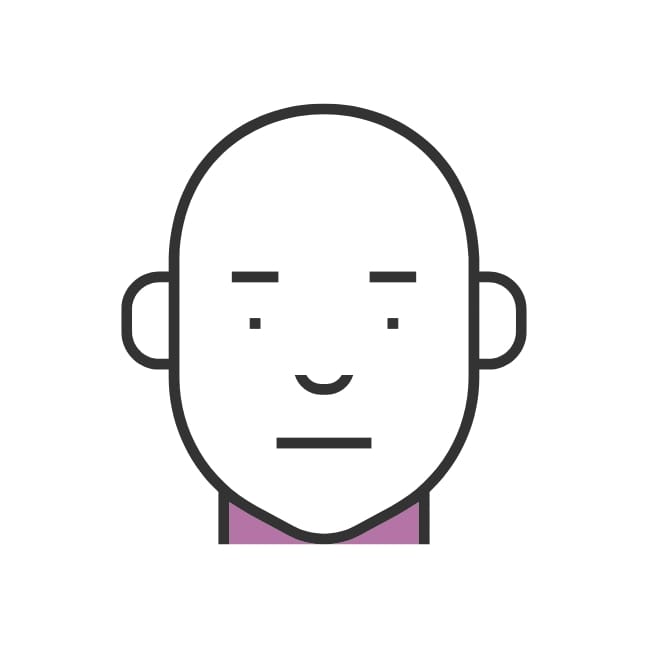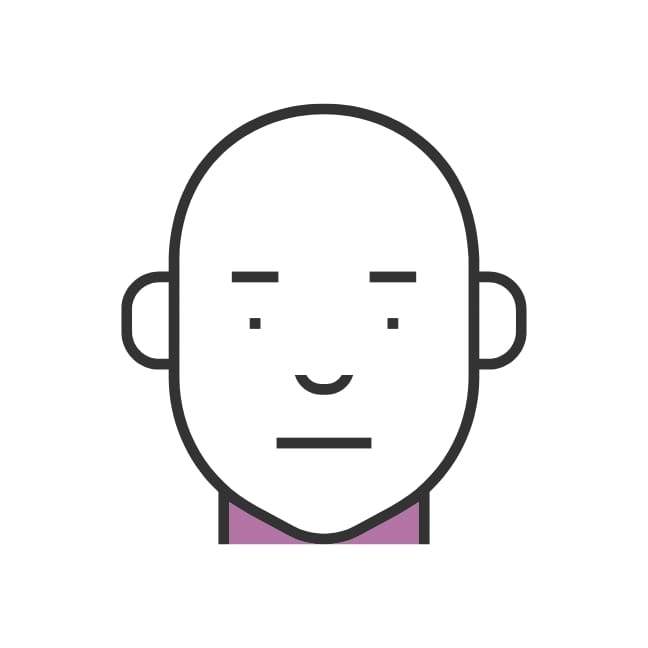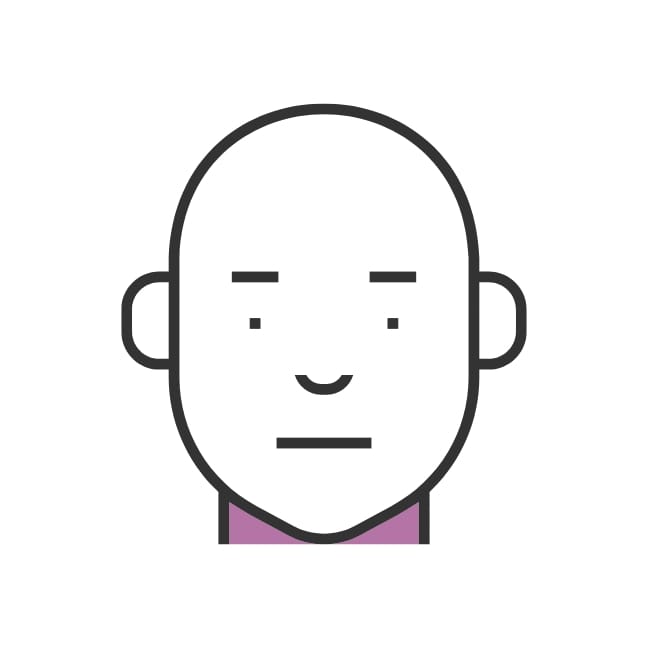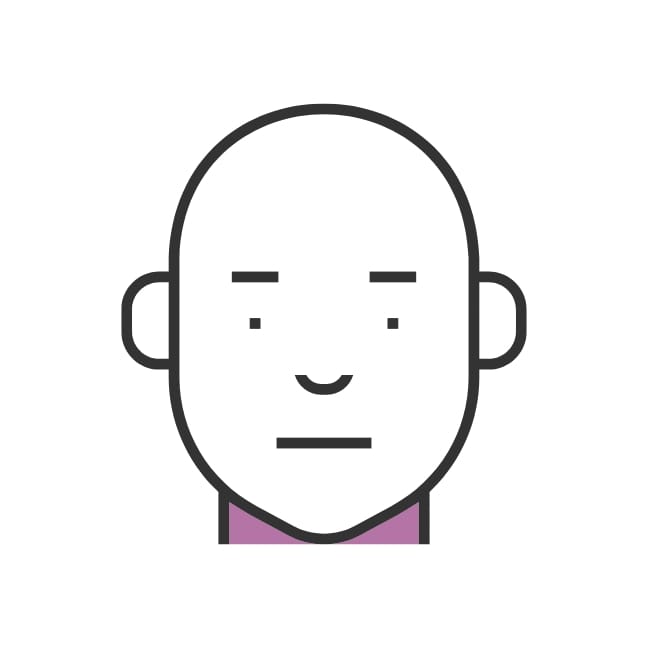病名検索について
疾患名や症状から診療科・部門を検索できます。病気についてや診断のプロセス、治療内容等のご説明も順次充実させていきます。ぜひお役立てください。
その他
眼科との連携でレーザー治療・抗VEGF抗体眼内注射など未熟児網膜症治療、脳外科との連携で新生児脳外科疾患の対応、ゲノム診療科との連携で染色体異常・先天奇形症候群への対応等も可能です。
廃用症候群・がん患者
小児疾患
中枢神経疾患や筋ジストロフィーなどの神経筋疾患、運動発達遅滞
NICU(新生児集中治療室)では、低出生体重児や新生児仮死等のハイリスク新生児極低出生体重児、超低出生体重児、低酸素虚血性脳症、脊髄髄膜瘤、先天性筋疾患、21トリソミーや口唇・口蓋裂の染色体、先天奇形系疾患他
ペインクリニック領域
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹後神経痛
- 三叉神経痛
- 繊維筋痛症
- 糖尿病性神経症
- 椎間板ヘルニア
- 脊柱管狭窄症
- 変形性脊椎症
- 閉塞性動脈硬化症
- 癌性疼痛
- 術後疼痛
など
手術室における全身管理、術後Acute Pain Service (APS)および集中治療
産後出血
胎児疾患
多胎妊娠
単胎妊娠
概日(がいじつ)リズム障害
睡眠-覚醒の時間帯が、社会生活(学校や会社等)での望ましい時間帯からずれてしまうもの。 極端に夜寝る時間が遅く、 朝寝坊になる睡眠相後退症候群が代表的です。看護師、警備などの交代勤務や海外との取引などを行っている方々に多く認められます。
特発性過眠症
睡眠時間を十分にとっていても、日中の過度の眠気が生じます。夜間帯の睡眠が長いことが多く、昼間の居眠りも1時間近くありますが、目が覚めたときの爽快感がないことが特徴で、ナルコレプシーの寝起きと異なります。
ナルコレプシー
夜間に十分に眠ったとしても、昼間に突然我慢できないほどの強い眠気に襲(おそ)われ、眠ってしまう病気です。
下記の4症状が特徴的です。
- 睡眠発作(突然の強い眠気が食事中・運転中・会話中・仕事中など、通常では考えられないような状況で起こり、眠り込んだ後は通常30分以内には目が覚め、非常に爽快感があります。しかし、しばらくするとまた眠気が襲ってきます。)
- 脱力発作(笑ったり、驚いたりしたときなどに、首や膝の力が抜け、ひどいときには倒れこんでしまいます。)
- 入眠時幻覚(非常に生々しく、時には恐ろしい内容の幻覚を見ます。)
- 睡眠麻痺(金縛りのことで、寝入りばなや目が覚めたときに体に力が入らなくなります。)
レム睡眠行動障害
睡眠中に突然、大声の寝言や奇声を発したりします。また、ベッドから転落したり隣で寝ている人を叩いたりすることもあります。 声をかけると比較的容易に覚醒し、夢の内容を明晰に思い出すことも特徴です。
むずむず脚症候群
レストレスレッグス症候群、下肢静止不能症候群とも呼ばれます。夕方ごろから夜間、就寝時にかけて、足に「むずむず」「ざわざわ」や、虫が這うような不快感で寝つきが妨げられます。鉄の欠乏も原因となります。
下記の4症状が特徴的です。
- 下肢の不快な異常感覚に伴い、足を動かしたいという強い衝動を感じます。
- 症状は、歩く、下肢を伸ばす、叩く、さするなどの運動によって改善します。
- 不快な感覚は、静かに横になったり座ったりしている状態で現れ、強くなります。
- 症状は、日中より夕方や夜(入眠時)に強くなります。
睡眠時無呼吸症候群を中心とした睡眠呼吸障害
『いびき』が主訴なことが多いですが、『夜間頻尿』もよく認められます。高血圧症、糖尿病などの生活習慣病の増悪因子になるため、『いびき』とあなどってはいけません。
敗血症性ショック
周術期管理
代謝不全
意識障害
循環不全
呼吸不全
ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍
甲状腺機能亢進症
甲状腺癌
乳腺病変のマンモトーム生検
がん遺伝子パネル検査
がん遺伝子パネル検査を保険診療で受けるためには、「標準治療がないまたは局所進行または転移が認められ標準治療が終了となった固形がんの患者さん(終了が見込まれる方を含む)」である必要があります。
どの段階で標準治療が終了(もしくは終了見込み)なのか、患者さんの全身状態が検査を受けられる状態かなどを担当医が見極めた上で、がん遺伝子パネル検査を受けられるかどうか判断します。
本来であればもっと早い時期にこのようなゲノム情報を知ることで治療の組み立てがしやすくなるのですが、現時点では保険での検査には制限があります。
当院では保険診療および自費診療によるがん遺伝子パネル検査を、当院の遺伝子医療センターや東京女子医科大学東医療センターと連携して実施しています。
PRRT(ペプチド受容体核医学内用療法)
当院では、神経内分泌腫瘍に対するPRRTであるルテチウムオキソドトレオチド(177LU-DOTATATE、ルタテラ®)を行っております。
これまで東京都内だけではなく全国からソマトスタチン受容体シンチグラフィ(オクトレオスキャン®)でソマトスタチン受容体陽性である切除不能又は遠隔転移を有する消化管、膵又は肺原発の神経内分泌腫瘍の患者さんに対して治療を行っており2023年度は14名の患者さんに治療を提供しました。
ソマトスタチン受容体シンチグラフィが未実施の場合は当院において検査をいたします。
治療を希望される場合には近藤教授外来予約をお取りください。
あるいは医療機関から問い合わせいただくことも可能です。
尋常性乾癬、乾癬性関節炎、掌蹠膿疱症
じんましん
アトピー性皮膚炎
更年期症候群
着床前診断
女性不妊症
その他婦人科良性疾患
子宮筋腫
子宮腺筋症
子宮内膜症
卵巣癌
子宮体癌
泌尿器科腫瘍
- 腎癌:全国一の手術症例数で、経験豊富な医師による診療を受けられます。分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬を中心とした薬物療法も全国トップレベルの経験数です。
- 腎盂癌、尿管癌:従来の手術療法から一歩踏み出して、患者さんの予後改善のためによりよい手術を心がけています。
- 膀胱癌:さまざまなステージの膀胱癌に対し、最適な治療を提供するよう心がけています。術前から手術、術後の治療や経過観察まで、関連病院と連携しながら治療を行います。
- 精巣腫瘍:病気のステージにより最適な治療を提供いたします。
小児脳神経疾患
胚細胞腫瘍
性腺の原始生殖細胞に由来する腫瘍です。体の正中線上に発生し、水頭症を合併して頭痛で発症することが多い脳腫瘍です。水頭症を合併している場合に水頭症治療を行った後に組織の生検を行うか、髄液中の特異的なマーカーを測定し診断を確定します。
視神経膠腫
脳腫瘍の中でも稀で、進行するにつれ視力障害が悪化します。当院では積極的な外科的治療を第一選択としております。一定の期間に一定の容積の摘出を行うことで、腫瘍の成長が停止あるいは退化する報告もあり、腫瘍が安定するまで根気強く外科的治療を継続しています。
小児悪性脳腫瘍
難治性脳腫瘍の治療には、多くの治療法を組み合わせた集学的治療が必要になります。当院では可能な限り手術による腫瘍の摘出と、それに引き続いて化学療法・放射線治療を行います。
小児脳幹部腫瘍
脳幹部(生命を維持する大事な機能が密集している)にできる腫瘍の総称です。世界中で様々な治療法が試みられておりますが、標準的治療として確立されているものは放射線治療のみです。限局的な腫瘍の場合は、その発生する場所によっては積極的な摘出を行うことがあります。限局的ではない腫瘍に対しては標準治療である放射線治療に則った治療を行いますが、放射線治療中の頭痛・吐き気・水頭症の軽減を目的とした外減圧術(頭蓋骨を一部外して頭の中の圧を軽減する手術)を、治療当初に行うことが挙げられます。
水頭症
髄液の産生と吸収のバランスが崩れ、頭の中に溜まった髄液が正常脳組織を圧迫し、頭痛や吐き気等の症状が出現します。水頭症という病態は、多様・複雑であり小児期だけの病態ではなく、成人まで幅広い年齢層で起こりえます。
脊髄髄膜瘤 脊髄脂肪腫
脊髄髄膜は、腰の部分に皮膚の欠損と髄膜瘤(膜に包まれた袋)の突出を認め、髄膜瘤の中には脊髄披裂を伴う脊髄を認めます。妊娠中の胎児エコーで脊髄髄膜瘤を認めた場合には、産科より連絡を受けた新生児科医・脳神経外科医・形成外科医師が出産時待機します。出産後は感染を回避する目的でも生後48時間以内に手術を行います。
同様に、腰にできる疾患として脊髄脂肪腫があります。本来、皮膚の下にあるべき脂肪組織が何らかの原因で脊髄まで入り込み、脊髄の成長(係留)により下肢の動きの異常・膀胱直腸障害を来します。
頭蓋変形
頭蓋骨を構成している縫合線の一部が早期に癒合してしまう、頭蓋骨縫合早期癒合症という病気があります。この病気は、赤ちゃんの頭の形が成長とともに変形が進行するのですが、単なる寝癖からくる2次的な頭蓋骨変形とは鑑別することが困難です。
ガンマナイフ治療
ガンマ線(放射線)を用いて、まるでナイフで病巣を切り取るような治療法です。開頭手術をしなくても、頭蓋内・脳内病変もしくは機能的脳疾患の治療・コントロールを可能とした、きわめて低侵襲な脳外科治療の一つです。転移性脳腫瘍、髄膜種、聴神経腫瘍、神経膠腫などの脳腫瘍や脳動静脈奇形(AVM)や三叉神経痛などの疾患の治療も行っております。
脊髄脊椎疾患
脊椎変性疾患
頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症、頚椎症性脊髄症、頚椎後縦靭帯骨化症、頚椎症性筋萎縮症などがあります。脊髄症状(歩きにくい、指が使いにくい、尿が出にくい、など)が進行あるいは持続する場合には、手術治療が推奨されます。
脊髄腫瘍
脊髄腫瘍とは、脊髄内に発生した腫瘍や、クモ膜,硬膜、神経鞘(神経を保護する膜)、さらに脊柱管内の軟部組織や椎体に発生した腫瘍により、脊髄や神経根が圧迫される病気の総称です。
脊髄硬膜動静脈瘻
脊髄硬膜動静脈瘻とは、脊髄神経根の硬膜貫通部近傍で動脈と静脈が直接吻合するため、動脈血が直接脊髄表面の静脈に還流し、脊髄からの正常な静脈血が静脈へ流れ込むことができなくなったために、脊髄うっ血を来たして各種の脊髄障害症状を起こす血管奇形の一種です。
椎体圧迫骨折
骨粗鬆症や転移性腫瘍などで骨がもろくなると、軽い衝撃で容易に骨が折れてしまうことがあります。もろくなった骨が加重に耐えかねてつぶれてしまうのが「椎体圧迫骨折」で、高齢に多く見られ70歳代の約30%に椎体骨折が認められると報告されています。
手根管症候群
正中神経は手関節の掌側の真ん中にあり、手根管という骨や靭帯によって囲まれたスペースを通過します。手根管症候群とは何らかの原因で手根管の内圧が高くなり、手根管内に存在する正中神経が圧迫されて痛みやしびれを引き起こす疾患です。
機能神経外科
本態性振戦
本態性振戦とは、明らかな原因がない(本態性)のにふるえ(振戦)がある状態を指します。軽度で、日常生活動作に及ぼす支障が軽微な場合には内服加療や経過観察が行われます。重症例では、視床の一部分を破壊することでふるえを止めることができます。
ジストニア(書痙など)
ジストニアという病気は、無意識に筋肉がこわばってしまう不随意運動の1種です。全身のあらゆる筋肉にジストニアは発症します。ジストニアの症状は、手や足、首や体幹など様々な箇所に発症しますが、その原因は脳からの指令の異常にあります。
痙縮(脳性麻痺など)
痙縮とは、筋肉に力が入りすぎて、手足が動かしにくかったり、勝手に動いてしまったりする状態のことです。原因として、脊髄損傷や脳血管障害,頭部外傷,脳性麻痺など様々ですが,痙縮を緩和することで日常生活動作(ADL)の改善などが期待できます。
神経障害性疼痛
神経障害性疼痛とは、体性感覚系(痛みを伝える神経)の損傷や疾患の直接的な結果として引き起こされる疼痛と定義されています。しかし、神経障害の有無を厳密に判定することが困難な場合も少なくありません。まずは、臨床上の有効性が確立された薬物療法や理学療法を行います。治療においては、痛みに対する正しい認識と日常生活動作の維持が必要です。これらの多面的な治療法のひとつとして、外科治療が有効な場合があります。
てんかん
てんかんは、およそ100人に1人という発症するという疾患と言われております。てんかんは、脳の一部の神経細胞の興奮が周囲脳組織に拡がり、発作症状を呈する焦点発作と、脳全体がいっせいに神経興奮が起こり、発作が起こる全般発作に分類されます。
頭部外傷
頭部外傷(外傷性脳損傷)
ヘルメットおよびシートベルト着用の義務化により、頭部外傷は年々減少傾向にあります。一方、高齢化社会の到来で、近年は転倒や転落による頭部外傷が問題になっています。また、児童虐待による頭部外傷やスポーツにおける脳震盪、高次脳機能障害など、解決すべき問題が多い分野です。
成人脳腫瘍
髄膜種
脳を覆っている膜から発生する腫瘍で、脳や血管などの構造物を圧迫しながら大きくなっていく腫瘍です。症状がある場合は積極的な治療を要することが多いですが、無症状で偶然見つかった場合は、個々に応じた判断・対応を必要とします。
神経膠腫(グリオーマ)
脳にある神経膠細胞が腫瘍化したもので、脳組織内に染み込むように浸潤するため、悪性脳腫瘍に分類されます。病理診断上、悪性度に応じてグレードが4つにわかれており、手術加療に加えて、放射線、化学療法など集学的な治療を行います。
下垂体腫瘍
下垂体とは脳底部に細い茎で繋がる1cmくらいの小さな器官で、全身のホルモンバランスをコントロールし、身体中の様々な機能を調節しています。下垂体腺腫、ラトケ嚢胞、頭蓋咽頭腫などの他に、視神経膠腫、胚細胞腫、髄膜腫、脊索腫といった腫瘍が発生します。
聴神経腫瘍
聴神経腫瘍とは、聴力を伝える神経の周囲を鞘のように被っているシュワン細胞から発生する腫瘍です。年齢や腫瘍の大きさ、症状を診断した上で経過観察、手術による摘出、ガンマナイフなどによる局所放射線照射、上記の組み合わせなどの治療方針を選択いたします。
その他の腫瘍
脳腫瘍の分類は現在130種類以上存在し、自然歴、部位、大きさなどにより治療法、手術法が異なるため個々の病態に併せた治療が必要となります。年齢や腫瘍の大きさ、症状で経過観察、手術による摘出、放射線治療、化学療法などの治療方針を選択いたします。葉状腫瘍
多発性内分泌腫瘍症
遺伝性疾患である多発性内分泌腫瘍症(Multiple Endocrine Neoplasia: MEN)の診療も行っています。MEN1型の副甲状腺機能亢進症では過不足のない治療を目指して適切な術式を個別に検討・判断します。消化器科や内分泌内科と連携し治療に当たります。MEN2型では遺伝子診断を行い、甲状腺髄様癌では腫瘍マーカー正常化を目指した根治手術を行う一方、両側副腎褐色細胞腫では機能温存の可能性を念頭に置いて管理方針を決め、治療に関しては当科で全て完結できます。また遺伝子陽性・未発症の保因者に対しては専門医として的確な医療情報を提供し、慎重な対応を心掛けています。
副腎
副腎腫瘍に対しては腹腔鏡下手術を標準術式としています。二次性高血圧の原因となるアルドステロン症、クッシング症候群、そして褐色細胞腫の外科治療が主ですが、副腎皮質癌の診療も行っています。
副甲状腺
原発性副甲状腺機能亢進症は我が国でも有数の手術症例数を経験しています。摘出すべき病変の位置を正確に診断することにより完治を実現し、手術成功率(治癒率)は99%です。極めて稀な副甲状腺癌症例も40例以上の経験を有し、的確な診療の確立に努めています。
甲状腺
甲状腺癌の手術方針を決めるには癌の進行度合いを見極めることが重要です。我が国の診療ガイドラインに即し、適切な管理方針を選択しています。1cm以下の経過観察も可能な乳頭癌には、手術または経過観察の選択を患者様と相談し決定しています。甲状腺良性腫瘍については頚部からアプローチする従来法に加えて、前胸部から内視鏡的にアプローチする内視鏡下甲状腺手術 Video-assisted neck surgery (VANS) を2022年から導入しました。
手肘
- 関節リウマチによる手指・手関節変形・肘関節変形
- ばね指
- 腱鞘炎
- ドケルバン病
- へバーデン結節
- ブシャール結節
- 母指CM関節症
- 手根管症候群
- 肘部管症候群
- 上腕骨外側上顆炎(テニス肘)
- マレット指変形
- 手指・手関節・肘関節の骨折(橈骨遠位端骨折、舟状骨骨折、中手骨骨折、肘頭骨折、上腕骨遠位端骨折等)
- 腱損傷
先天性心疾患
重症心不全、心臓移植
その他
- 鼠径ヘルニア
- 臍ヘルニア
- 白線ヘルニア
- 大腿ヘルニア
- リンパ管腫
- 血管腫
- 乳糜腹水
- 腹部鈍的外傷急性腹症
- 腹腔内異物
- 腹腔内腫瘍
- 腹腔内膿瘍
- 腹膜透析カテーテル挿入疾患
- 腹腔内カテーテルトラブル
泌尿生殖器疾患
- 副腎腫瘍
- 水腎症
- 腎盂尿管移行部狭窄症
- 膀胱尿管移行部狭窄症
- 膀胱尿管逆流症
- 後部尿道弁
- 無機能腎
- 馬蹄腎
- 精索静脈瘤
- 停留精巣
- 遊走精巣
- 精巣捻転
- 急性陰嚢症
- 卵巣捻転
- 卵巣腫瘍
- 新生児卵巣嚢腫
- 尿膜管遺残症
- 総排泄腔症
- 性分化異常症
- 陰唇癒合症
消化管疾患
- 食道アカラシア
- 先天性食道閉鎖症
- 先天性食道狭窄症
- 食道裂孔ヘルニア
- 胃食道逆流症
- 肥厚性幽門狭窄症
- 胃軸捻転症
- 十二指腸潰瘍穿孔
- 先天性十二指腸閉鎖・狭窄症
- 腸回転異常症
- メッケル憩室
- 臍腸管遺残症
- 腸管重複症
- 腸重積症
- 虫垂炎
- 潰瘍性大腸炎
- 直腸脱
- 乳児痔瘻
- 肛門周囲膿瘍
- 裂肛
- ヒルシュスプルング病
- 鎖肛
- 内ヘルニア
- 癒着性腸閉塞
膵臓がん
膵がんは非常に悪性度が高く、また見つかった時点で既に進行していることが多いため、他の臓器のがんと比較すると患者全体の治療成績は不良です。
しかし、膵がんであっても早期に発見して適切な治療を受ければ、高い確率で治すことが可能です。
また、ある程度進行した膵がんに対する治療も、抗がん剤治療の発展に伴って大きく改善してきました。
一般的に、がんの治療成績をよくするためには、早期発見と治療法の進歩の2つが鍵になります。
胆道がん
胆道がんの根治的治療法は外科切除です。
かつては手術をしてもがんを完全に切除しきれない場合が多かったり、手術後の合併症率や死亡率が高いことが問題になっていました。
しかし、近年ではCTなど画像診断の進歩と手術の定型化により、手術前にがんの範囲、周囲の血管や肝臓との位置関係の把握がより正確にできるようになったこと、術前術後の体調管理上の様々な対策と工夫が進んだことによって、手術成績が向上しました。
なお、手術では明らかにがんをすべて切除しきれない場合(切除不能)や、切除できたように見えても目に見えない(検査では指摘できない)レベルでがんが残る可能性が非常に高い場合(切除可能境界)には、化学療法(抗がん剤治療)を数か月間行います。
その結果、がんが縮小したり、がんが大きくならない、もしくは新たな転移が見つからなければ、あらためて手術を行うことを検討します。
また、がんの進行度によって、手術の後に抗がん剤治療(術後補助化学療法)を行うことをお勧めする場合があります。
肝臓がん
肝臓の腫瘍に対して行われる治療には、肝切除術、ラジオ波・マイクロ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法、抗がん剤治療、放射線治療、肝移植などがあります。
肝内結石症に対しても肝切除術が行われます。
肝嚢胞に対しては、エタノール注入療法や、肝嚢胞開窓術が行われます。
-
- 腹腔鏡下肝切除術
肝臓は右の肋骨の奥深いところに納まっているため、開腹手術では体壁をかなり大きく切開する必要がありますが、腹腔鏡手術ではいくつかの小さな穴と肝臓を取り出すための最低限の切開ですみます。
もうひとつは出血量が少ないことです。
肝臓内の血管では血圧が比較的低いため、気腹によってお腹の中の気圧を上げた状態で手術を行うと、切断中の肝臓の表面からの出血量が少なくなります。
もちろんすべての肝切除術が腹腔鏡手術に適しているわけではありませんが、適切な選択と適切な技術によって開腹手術と変わらない手術成績が得られることはすでに証明されています。 - 肝内胆管がん(胆管細胞がん)の治療
肝内胆管がんは、肝細胞がんと比較すると手術による治療成績が不良で、手術後の5年生存率は一般的に30〜40%くらいでした。
しかし近年は、手術と化学療法(抗がん剤治療)を組み合わせることにより5年生存率が約60%まで改善しています。
当科でも、手術の前後に積極的に化学療法を行うことで、治療成績が大幅に改善しています。
- 腹腔鏡下肝切除術
炎症性腸疾患
- 潰瘍性大腸炎
若年者に多い疾患で近年増加傾向にあります。
内科的治療が中心ですが治療抵抗性の難治例や重症例では手術が必要になります。
手術は自然肛門を温存する術式が基本です。
当科では体に優しい腹腔鏡手術を積極的に取り入れ小さな創で手術を行っています。
手術は2回にわけて行います。
1回目の手術では、大腸をすべて切除して小腸にためる部分(回腸嚢)を作って肛門につなぎます。
大腸をすべて切除するのは、炎症の強い部分だけを切除すると、術後に残った大腸に同じような炎症が起きることや癌が発生する可能性があるためです。
1回目の手術では、つなぎめの安静を図るため一時的な人工肛門を造設しますが、2回目の手術で人工肛門を閉鎖するので人工肛門はなくなります。
最近は高齢者の患者さんが増加傾向にあり癌化例が増加しています。
癌化例では根治性を重視しつつ機能温存も考慮した手術を行っています。
また、潰瘍性大腸炎では、穿孔(腸に穴が開くこと)、大量出血、中毒性巨大結腸症などを重篤な状態に陥いることがあります。
この場合は速やかな治療が必要となり緊急手術で対応します。 - クローン病
潰瘍性大腸炎と同様に若年者に多い疾患で近年増加傾向にあります。
食事療法や内科的治療が中心ですが、穿孔、大量出血、腸管狭窄、膿瘍(膿がたまること)、内瘻(腸管と周囲の臓器がつながること)などを併発すると手術が必要となります。
手術では、体に優しい腹腔鏡手術を積極的に取り入れています。
クローン病は若年者が多く、長期経過の中で再燃し複数回手術が必要となることが多い疾患であり、複数回手術による腸管切除で短腸症候群(腸が短くなって栄養障害などがおきること)になることを回避する術式が選択されます。
腸管を温存するために病変部の切除は最小限にとどめ、狭窄形成術(狭窄状態に対し腸管を切除しないで腸管の内腔を拡げる方法)や再燃を少なくする吻合法の工夫なども行っています。
また、クローン病に高率に併発する、痔瘻や肛門周囲膿瘍に対しては肛門機能温存を基本とした手術を行っています。
大腸がん
- 腹腔鏡手術
大腸切除術の大半を腹腔鏡手術で行っています。
傷や痛みが小さく術後の回復が早いだけでなく、繊細で出血量の少ない手術が可能という点が腹腔鏡手術のメリットです。
当科には現在、日本内視鏡外科学会技術認定医が3名在籍しています。
術者、助手、そして看護師が一丸となり安全な手術治療を行います。 - ロボット手術
手術支援ロボットであるダビンチを使用した直腸がんに対するロボット支援下手術は、2018年に保険診療として実施可能になりましたが、当科ではこれに先駆けて2017年より実施してきました。
また2024年より結腸がんにもロボット支援下手術を開始しました。
奥行きのある鮮明な三次元ハイビジョン画像や手ブレ防止機能、自由度の高い多関節鉗子操作などによって有効性を発揮します。 - 肛門温存手術
肛門に近い直腸がんでは、がんの切除後に永久人工肛門が必要となる場合があります。
しかし、がんの進行状況によっては、がんを確実に取り除いたうえで、肛門の筋肉の一部だけを切除して肛門を温存する手術方法(括約筋間直腸切除:ISR)が選択できます。
このような治療方法が普及したことによって、以前は永久人工肛門が必要だった患者さんの多くが、肛門を温存できるようになりました。
また進行した直腸がんには、手術前に放射線治療や抗がん剤治療を行って、肛門の温存や治療成績の向上を図っています。
胃がん
診断がついた時点でのステージ(進行の度合い)や患者さんのもともとの健康状態をもとに、手術だけではなく抗がん剤治療を含めた様々な治療方法の中から最適な治療法を、患者さんとよく相談したうえで選択します。
当科ではロボット支援下手術を積極的に行っています。
胃がんに対するロボット支援下手術は腹腔鏡下手術よりも手術に伴う合併症を少なくすることができるという実績が報告され、2018年4月より保険診療として受けることが可能になりました。
さらに腹腔鏡手術よりも生存率の向上が得られるとも報告もされており、当科では可能な限り、ロボット支援下手術を行なっております。
食道がん
- 外科手術
ステージI~IIIまでが外科手術の適応となります。
大半の食道癌が発生する胸部食道に病変がある場合、食道亜全摘術が標準の術式となります。
下図のように、食道の大部分と胃の一部を周囲のリンパ節も含めて切除し、形成した胃(胃管といいます)を首または胸まで持ち上げて、残りの食道とつなぎあわせます。
ステージII, IIIに対してはまず化学療法(DCF療法など)を行い、その後に手術を行うことによって予後が向上することが分かっています。 - 化学療法
化学療法・緩和ケア科と連携して行っています。
上述の術前化学療法のほかに、切除不能進行がんや再発がんに対しては、最新のガイドラインに従って、腫瘍細胞の分子生物学的特徴や腫瘍量、年齢などを考慮し、免疫チェックポイント阻害剤を併用した化学療法も行っております。 - 放射線療法
放射線腫瘍科と連携して行っています。
周囲の正常組織へのダメージが少なくなるよう、腫瘍の形や体積に応じて照射量を調整する強度変調放射線治療(IMRT)が行える設備を有しており、効果的かつ副作用の少ない照射を行うことが可能です。 - 内視鏡的切除
腫瘍の広さなどにもよりますが、基本的には深達度が粘膜層までにとどまっている場合、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が適応となります。
この専門家集団である消化器内視鏡科は消化器病センターとして当科と一体を成しており、密に連携しながら症例の受け渡しを行っております。
小児の心疾患・不整脈疾患
先天性心疾患(小児・成人にかかわらず)
頭頸部の良・悪性腫瘍
耳疾患
- めまい症(良性発作性頭位めまい症、メニエール病、前庭神経炎、その他の内耳性めまい)
- 成人と小児の難聴(突発性難聴、小児難聴、補聴器)
- 耳管機能不全
- 顔面神経麻痺
- 中耳炎(急性、慢性、滲出性、真珠腫)
睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置作製
口腔機能低下症
歯が原因の炎症、感染症
歯や口の外傷、顎の骨折
唾液腺疾患(顎下腺・舌下腺)
口内炎・口腔粘膜疾患
薬剤関連顎骨壊死、放射線性顎骨壊死
顎関節症
顎骨のう胞・腫瘍
親知らずの抜歯
歯科インプラント治療
顎変形症
口腔がん
胸部外傷
気管内疾患(気管気管支内腫瘍、気管気管支狭窄など)
胸壁腫瘍(悪性、良性)
胸膜疾患(良性、悪性胸膜中皮腫など)
感染性・炎症性肺疾患
膿胸
気胸、肺嚢胞
重症筋無力症
縦隔腫瘍(良性、悪性)
肺腫瘍(良性)
転移性肺腫瘍
視神経症
視神経炎
ベーチェット病
原田病
サルコイドーシス
ぶどう膜炎
眼内炎
眼瞼下垂
弱視
斜視
細菌性・ウイルス性結膜炎
アレルギー性結膜炎
角膜感染症
ドライアイ
網膜色素変性症
中心性漿液性脈絡網膜症
黄斑上膜
黄斑円孔
網膜剥離
網膜動脈閉塞症
網膜静脈閉塞症
加齢黄斑変性
糖尿病網膜症
緑内障
白内障
めまい
慢性頭痛
てんかん
意識障害
神経感染症
末梢神経疾患
脳血管障害
脳動脈瘤
脳動脈瘤とは、脳動脈の血管壁が風船のように瘤状に膨らむ状態です。脳動脈瘤の多くは、未破裂の状態で発見され無症状です。しかし、破裂すればクモ膜下出血を来しますし、中には徐々に増大して周囲の神経を圧迫することで症状を来すこともあります。
もやもや病
内頚動脈、前大脳動脈、中大脳動脈、後大脳動脈といった脳内の主幹動脈が進行性に閉塞し、脳内の細い血管(穿通枝)が拡張、側副路を形成していく(もやもや血管と呼ばれます)疾患で原因は詳しくはわかっていません。進行していく過程で様々な症状を呈し、頭痛、てんかん、脱力発作、しびれ、失語症などの一過性脳虚血発作、脳梗塞、脳内出血で発症します。小児では難治性頭痛、あるいは一過性脳虚血発作で、成人では出血で発症する例も多く報告されています。近年は高次脳機能障害も注目されています。
閉塞性脳血管障害
閉塞性脳血管障害とは、内頚動脈や中大脳動脈が動脈硬化により閉塞(時に高度狭窄)している状態を指します。閉塞による脳血流低下や、閉塞時の塞栓物質により、脳梗塞を引き起こすことが知られています。
頸動脈狭窄症
頚動脈狭窄症とは、頚動脈に動脈硬化性粥状変化(プラーク)が形成され、局所で細くなっている状態(狭窄)です。狭窄の進行による脳血流低下や、狭窄部からの塞栓物質により、脳梗塞を引き起こすことが知られています。頚動脈狭窄症に対する治療は、第一に脂質異常症改善薬や抗血小板薬を含む内科的治療が選択されます。
脳動静脈奇形(AVM)
脳動静脈奇形(AVM)とは、脳内で動脈と静脈の直接吻合を生じている先天性疾患です。吻合部には異常な血管塊(ナイダス)が認められ、動脈の圧が直接静脈に加わるため、ナイダスが徐々に増大することがあり、ナイダスが増大して破裂すると、クモ膜下出血や脳出血などの出血を起こします。また痙攣発作、精神症状、痴呆症状、頭痛、脳虚血発作、心不全を引き起こすことがあります。
顔面けいれん
顔面けいれんは、人前での緊張、ストレス、疲れ、強い閉眼などの顔面筋の運動などで誘発されやすく、初めのうちはあまり気にならない程度でも、徐々に悪化することがあります。誰にも相談できずに一人で悩んでいることも多く、中には、うつ状態になっている患者さんもいます。
特発性三叉神経痛
顔面の感覚神経である三叉神経の領域に、通常片側に発作性の数秒から数分続く激痛が繰り返して起こるものです。洗顔、髭剃り、歯磨き、咀嚼(そしゃく)などで誘発され、時には冷たい風にあたるだけで痛くなることもあります。痛みは患者本人にしかわからず、他人に理解が得られなくて悩んでいる患者様も多くいるようです。
性腺疾患
副腎疾患
カルシウム・骨代謝疾患
甲状腺疾患
間脳下垂体疾患
糖尿病合併症(神経障害、腎症など)
糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病、妊娠糖尿病)
透析困難症や透析患者の合併症
その他の全身疾患に伴う腎疾患
アミロイドーシス
血管炎
尿細管間質性腎炎
水・電解質異常
多発性嚢胞腎
遺伝性腎疾患
膠原病
ネフローゼ症候群
急性糸球体腎炎
慢性糸球体腎炎
血液透析・腹膜透析
腎移植
水腎症、膀胱尿管逆流、尿路感染症
学校検尿異常
パーソナリティ障害
器質性精神障害
認知症
嗜癖性障害
睡眠障害
摂食障害
解離性障害
身体症状症
適応障害
心的外傷後ストレス障害
強迫性障害
統合失調症
双極性障害
うつ病
不明熱
若年性皮膚筋炎
若年性特発性関節炎
神経代謝
内分泌・代謝
筋疾患
てんかん(ケトン食療法連携チーム)
神経発達
小児リウマチ免疫
消化器
アレルギー・免疫
自己免疫性胃炎
ヘリコバクター・ピロリ胃炎
消化管リンパ増殖性疾患
大腸憩室出血をはじめとする下部消化管出血
胃・十二指腸潰瘍出血などの上部消化管出血
大腸ポリープ
食道、胃、十二指腸、大腸の早期癌
急性膵炎・慢性膵炎
胆管結石・胆嚢結石・急性胆管炎
食道胃静脈瘤
大血管疾患
末梢血管疾患
心不全・心筋症
不整脈
急性・慢性呼吸不全
肺循環障害(肺塞栓、肺梗塞)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
気管支喘息・咳喘息、アレルギー性肺疾患
良性および悪性腫瘍
その他のリウマチ性疾患
リウマチ性多発筋痛症
乾癬性関節炎
脊椎関節炎
再発性多発軟骨炎
成人発症スチル病
抗リン脂質抗体症候群
多発性筋炎・皮膚筋炎
全身性強皮症
関節リウマチ
高血圧を伴う各種疾患
血液疾患
- 先天性溶血性貧血
- サラセミア
- 遺伝性球状赤血球症などの赤血球膜異常症
- 赤血球酵素異常症
- 不安定ヘモグロビン症
- ダイアモンド・ブラックファン貧血
- 先天性赤血球形成異常性貧血(CDA)
がんゲノム
- がんゲノムパネル検査
- リキッドバイオプシー(Guardant360)
- マルチジーンパネル検査
- コンパニオン診断(BRCA1/2:乳がん・卵巣がん・前立腺がん・すい臓がん, MSI検査)
- OncotypeDx
先天症候群
- プラダーウィリー症候群
- ウィリアムス症候群
- カブキ症候群
- コルネリア・デランゲ症候群
- ソトス症候群
- ヌーナン症候群
- コステロ症候群
- CFC症候群
- 脆弱X症候群
- Dysmorphology診断
染色体疾患
- ダウン症候群
- 5pモノソミー
- 4pモノソミー
- 22q11.2欠失症候群
- 1p36欠失症候群
- パリスター・キリアン症候群(Pallister-Killian症候群)
- クラインフェルター症候群(Klinefelter症候群)
- ターナー症候群(Turner症候群)
神経・筋疾患
- 脊髄性筋萎縮症(SMA)
- 球脊髄性筋萎縮症(SBMA)
- ハンチントン病
- 脊髄小脳変性症(SCA)
- 大脳白質変性症
- ペリツェウス・メルツバッハ病
- デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)
- ベッカー型筋ジストロフィー(BMD)
- 福山型筋ジストロフィー(FCMD)
- 筋強直性ジストロフィー(DM1)
- 神経線維腫症I型(NF1)・II型(NF2)
- てんかん
- 水頭症
- 神経発達症
- 自閉スペクトラム症
- 知的能力障害(知的障害)
その他の血液疾患
- 再生不良性貧血
- 骨髄異形成症候群
- 鉄欠乏性貧血
- 悪性貧血
- 自己免疫性溶血性貧血
- 遺伝性球状赤血球症
- 発作性夜間ヘモグロビン尿症
- サラセミア
- 異常ヘモグロビン症
- 単クローン性免疫グロブリン血症
- 原発性マクログロブリン血症
- 伝染性単核球症
- 慢性活動性EBウイルス感染症
- 特発性血小板減少性紫斑病
- 血栓性血小板減少性紫斑病
- 播種性血管内凝固症候群
- 分類不能型免疫不全症(CVID)
- 先天性血小板機能異常症
- 先天性免疫不全症など
血液がん
- 急性骨髄性白血病
- 急性リンパ性白血病
- 急性混合性白血病
- 慢性骨髄性白血病
- 慢性リンパ性白血病
- 骨髄増殖性腫瘍(真性赤血球増加症、原発性骨髄線維症、本体勢血小板血症)
- 悪性リンパ腫
- 多発性骨髄腫
- 成人T細胞白血病・リンパ腫など
その他さまざまな血液浄化療法が適応となる疾患
わが国では上記の疾患を含め約40種類の疾患が血液浄化療法の適応疾患となっています。
これらの多くは、稀な疾患ですが、重症化する可能性があります。
重症化の予防および他の治療法をサポートする目的で、血液浄化療法が活用されています。
自己免疫性神経筋疾患(重症筋無力症、ギラン・バレー症候群など)
血液中に神経・筋肉に対する抗体ができることで、これらの働きが障害される疾患に対して、その抗体を除去するために血漿交換を行っています。