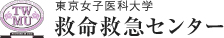後期臨床研修プログラム
救急科専攻医(後期臨床研修)プログラム
(救急科専門医取得後キャリアアッププログラム)
※見学は救命救急センター医局dem.ag@twmu.ac.jpまで。随時受け付けております。
一般目標
行動目標
〈医療人として必要な基本姿勢・態度〉
患者 – 医師関係
- 患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な人間関係を確立する為に、
患者の社会的背景を理解し適切な対応ができる。 - 医師、患者・家族がともに納得できる医療を行う為のインフォームド・コンセントが実施できる。
- 行政、司法担当者と良好な協調関係を構築できる。
チーム医療
- 医療チームの構成員としての役割を理解し、保険・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメンバーと強調する為に、
指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションできる。 - 上級及び同僚医師や他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。
- 同僚及び後輩への教育的配慮ができる。
- 患者の転入・転出に当たり情報を交換できる。
安全管理
- 患者及び医療従事者にとって安全な医療行為を遂行し、安全管理の方策を身に付ける。
危機管理を参画するために、医療を行う際の安全確認の考え方を理解し実施できる。 - 院内感染対策(Standard Precautionsを含む)を理解し実施できる。
東京女子医科大学救命救急センターの現状と未来像
当センターは3代目教授・センター長が就任して間もないですが、長きにわたる歴史と伝統があります。特に1990年代には国内有数の外傷・外科系救急の先駆けとして活躍しました。現センター長は米国での3年間の外傷センターでの臨床経験をはじめ、国内で10年の外科修練と10年の救急集中治療の修練の経歴を持つ外傷・外科系救急のスペシャリストです。各種重症疾患の診療にも精通しており、臨床、教育、研究のあらゆる面で救急医を目指す未来ある医師の育成、支援を行ってまいります。
教室の歴史
1989年に東京女子医科大学病院救命救急センターが設立され、旧第二外科学教室の救急グループとして属し発展した。
1995年に講座となり、1996年に鈴木先生が救命救急センター長、救急医学講座主任教授に就任され、外傷、外科を中心とする教室に発展させた。
教室の使命
- 臨床、特に外傷外科、ACSを中心とした外科系救急を充実させる。
- 二次~三次まであらゆる疾患に対応できる強固な組織を構築する。
- 臨床・教育・研究のバランスを維持しつつ、国際化を図り世界に通用する教室とする。
教室の目標
- 外傷センター、ACSセンターを確立し、重症搬送、転院を積極的に受け入れる。
- 初療室手術(開胸・開腹など)、緊急手術体制を確立する。
- 研究に取り組みやすい環境の構築、学会発表・論文投稿を推進、科研費への応募を行う。
- 新棟設立に向けて適応症例を増やし、Hybrid Roomを取得する。
- 救急救命士、NP(臨床看護師)等を増員。Dr Car導入を目指す。
- 国内外臨床留学、研究留学を推奨する。
- 円滑な専門医等の資格取得を目指す。
立地
当院は新宿駅から直線で約2km、副都心、首都中心部に位置しています。そのため、人口過密地域でもあり、地域の救急を守る組織の一角として高度の医療を提供すべく活動を行っています。近隣には著名な5病院が位置するも、救急受入要請台数は年間1万台を超えており、救命救急センターとして重症症例のみならず地域の二次救急への対応も担っています。当センターは利便性に優れ、バス4路線が学内発着、都営地下鉄大江戸線若松河田駅、都営地下鉄新宿線曙橋駅から至近にあるなど、多様な交通網でアクセスが容易となっています。



このような環境の中、東京都区西部で発生した多くの救急搬送事例を受け入れています。
学内構想
現在、救命救急センターは東病棟で運営をしています。B1Fが医局とDMAT運営室、1Fが初療室および救命救急集中治療室(E-ICU)12床、6Fが一般病棟20床となっています。今後、初療室・ICUの拡張と増床を見込んでいますが、さらに数年後には現在更地となっている部分に新病棟を建設し移転する計画です(図)。新病棟は1Fに救命救急初療室、上階に手術室、専用集中治療室・病棟を設置し、最新設備を備えた救命救急センターとなり、効率的な運用と高度な医療を提供します。

診療内容
当救命救急センターでは以下の多彩な疾患に対する治療を行っています。
重症内因性疾患に対する救命・集中治療
代謝障害、各種感染症(肺炎、軟部組織感染症など)、敗血症、臓器障害、心不全、呼吸不全、急性腹症、脳血管・脳神経障害、消化器系疾患
各種外傷診療
頭部外傷、胸腹部外傷、脊椎、骨盤・四肢の外傷、多発外傷
中毒
急性薬物中毒、各種特殊毒物暴露、一酸化炭素中毒
アナフィラキシーショック
心肺停止
環境障害
熱中症、低体温症、潜水病、高山病
広範囲熱傷
以下、当院で行っている主な治療です。
各種緊急手術、外来での緊急開胸、開腹手術
呼吸管理、循環管理
心肺蘇生後体温管理療法(低体温療法)
広範囲熱傷集中治療管理、植皮術
高気圧酸素療法(イレウス、高山病・潜水病、CO中毒、ガス壊疽・壊死性筋膜炎)
各種体外循環(ECMO、IABP、CHDF、PMX-DHP、血漿交換)
各種カテーテル検査・治療(IVR、CAG、緊急ペーシング)
当院は医学部附属の総合病院であり、各診療科が高度の医療を提供しています。救命救急センターにおいても、救急科専門医が主体となってその治療方針を決定し、脳神経外科、形成外科、整形外科など各科の協力のもと高度な医療を提供しています。

救命ICU12床

高気圧酸素療法(HBO)

重症初療室
大学病院で研修する意義
東京女子医科大学救命救急センターは大学医学部附属病院に属し、また足立医療センター、八千代医療センターを含めた3病院のいずれもが救命救急センターの指定を受けています。従って保有病床数、症例数は十分にあり、様々な環境で高度な医療を学ぶことができます。
足立医療センター 450床

足立医療センター 450床
八千代医療センター 500床

八千代医療センター 500床

本院 1,193床
大学病院が一般の病院と異なるところは、教育、臨床、研究の比重です。また、大学での研究歴が学位取得につながります。
大学臨床研修・修練の意義
大学病院

一般病院

臨床
専門医機構認定の専門医資格を所持することは、診療経験を重ねてゆく上で重要な事項となっております。救急領域においては基幹領域である救急科専門医資格にとどまらず、外科、内科、小児科、産婦人科、麻酔科、放射線科、整形外科等の様々なサブスペシャリティ資格を取得することが推奨されています。特に集中治療専門医の取得をお勧めしていますが、これは救急初期診療のみならず、重症疾患の集中治療も担える医師を目指していただくためです。東京女子医科大学救命救急センターでは大学病院の特色を生かし、効率よく多様な専門医、指導医資格の取得することができ、また、救命救急ICUに加え、一般ICU、CCU、SCUを有する環境において幅広く集中治療の研修をすることができます。救命救急センターICUと一般ICUはそれぞれが学会認定施設となっており、いずれの研修歴も機構専門医資格の取得に有効です。
学会専門医・指導医資格

救命救急ICUでは多様な救急疾患を扱います。あらゆる重症疾患の集中治療を経験し、救急科専門医、集中治療専門医を取得します。また、各種サブスペシャリティ専門医については学内、学外での研修を含め潤沢な研修環境を提供しており、個々の希望に沿ってカリキュラムを組んでいただき、教室としてはこれを支援します。
消化管内視鏡検査、気管支鏡検査、超音波検査の取得は救急医として不可欠な手技として挙げられます。救命救急センターの後期研修医、専攻医はそれぞれの修練・技能習得を院内もしくは分院の各診療科・各センターにおいて行う体制を確立しています。したがって、後期研修中に各種専門医(消化器内視鏡専門医など)を取得することが可能となっています。すなわち、あらゆる技術、知識、資格を取得することが単一施設で可能なことが当院の特徴です。もちろん、一つの病院に限定した修練は、限られた技能と偏った知識に留まることも考えられるため、国内外の各施設での修練も推奨しています。
多様なサブスペシャリティーの選択

以下は某救命救急センター医師のキャリアモデルですが、多くの医師が子育てをしながらも救急医として確実にキャリアを重ね、生涯にわたり使える技能と資格を取得の上、教育、研究、臨床にバランスの取れた医師人生を送っておられます。また、家庭と職場で過ごす時間のバランスもしっかりと取られています。東京女子医科大学では社会で活躍する女性医師を育成することを理念に置き、そのためにはしっかりした職場環境を提供し、家庭との両立が負担なくできるように配慮しています。最近では男性の育児参加、育休取得も重要視されている中で、性別を問わず誰にとっても過ごしやすい環境をどの施設にも劣らず提供することに力を注いでいます。








東京女子医科大学救命救急センターでは、センター内にとどまらない様々な研修機会を提供しています。相互の人的交流があってこそ安定した知識や技能のアップデートが行え、また、様々な環境で医療を経験することが、生涯にわたり多様な疾患に対する診療、研究活動、および教育・指導能力の獲得につながるものと理解しています。したがって、希望する者には積極的に各施設への研修が受けられるように取り計らいます。
東京女子医科大学救命救急センター・救急医学教室
教育・研修体制




関連病院・国内研修施設
東京女子医科大学附属足立医療センター
東京女子医科大学附属八千代医療センター
静岡赤十字病院
国立病院機構災害医療センター
東京科学大学病院
日本医科大学病院
埼玉県済生会加須病院
埼玉医科大学国際医療センター
亀田総合病院
慈泉会相澤病院
横浜市立みなと赤十字病院
静岡県立総合病院
戸田中央総合病院
外科系・外傷救急医を目指すものにとって単一施設で十分な症例を得て修練を積むには足りないところもあるため、積極的に他施設での研修を推奨しています。一方で、当センターのスタッフは様々な外科症例を扱うことができ、科内で完結する外科症例も多いため、外科系、内科系の専攻を問わず、当院での研修中にもあらゆる手技に精通してもらうようにしています。
腹部刺創症例に対する緊急開腹手術
来院時 出血性ショック、腸管脱出
所見 結腸・下大静脈損傷
術式 腸管切除吻合、下大静脈修復術


海外臨床留学
特に外傷・外科系救急専門医を目指すものにとって国内だけで修練を行うには症例が不十分であることは否めません。日本が極めて平和な国で医療体制が充実しているため、各施設あたりの症例数が限定的となるためです。そこで、当教室では海外臨床留学をお勧めします。センター長は3年の海外臨床経験のほか、複数の施設での研修で交流を深めています。USMLE step 3、ニューヨーク州医師免許を取得し、ニューヨーク州ニューヨーク医科大学附属ウエストチェスターメディカルセンターのLevel Iトラウマセンターで2年間、Trauma and Acute Care Surgery Fellowの研修歴があります。その経験を踏まえて、ぜひとも外傷外科、外科系救急を目指す先生方には積極的に海外での臨床研修を受けていただきたいと考えています。もちろんUSMLEの合格とECFMG certificateは必須ですので、その支援もさせていただきます。
Westchester Medical Center, NY
Level I Trauma center

外傷外科
血管外科
外科集中治療
Montefiore New Rochelle Hospital, NY
Level II Trauma Center

外傷外科
血管外科
救急外科
- 外科手術を経験
- 多発外傷、刺創、銃創などの外傷の診断・治療、手術、集中治療を経験
- 血管外科フェローとして手術を経験
- 学生講義(チュートリアル、ミニレクチャー)、研修医教育を担当
今後目指す救命救急センター像
当センターは三次医療機関であり、より一層の救急診療体制の充実を図っています。そこで、救急医療の専門を目指す若手医師には是非とも教室とともに成長していただきたいと考えています。
研究
当センターは大学附属病院の一部であり、研究も重要な役割と捉えています。救急医学における研究は臨床研究と基礎研究に分かれますが、どちらも選択することが可能です。基礎、臨床にかかわらず研究の基本姿勢として、多くの症例を経験することが極めて重要です。診療の質と量を高め、そこで得た経験を蓄積して症例報告もしくは臨床研究という形で学会発表や論文掲載という形で表現し、さらに基礎、臨床を問わず研究へとつなげられるようにします。また、科学研究費への応募、補助金の獲得、治験への参加などを通じて研究資金の獲得を行い、さらに、学会主導研究などの他施設共同研究への参画もしていただきます。
臨床研究・基礎研究 教室全員の参加

研究論文・臨床論文・症例報告・学会発表(国内・海外)
大学敷地内には東京女子医大と早稲田大学による医工融合研究教育拠点であるTWIns(Tokyo Women's Medical University and Waseda University Joint Institution for Advanced Biomedical Sciences) を有し、そこに東京女子医科大学先端生命医学研究所 ABMES (The Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science) があります。そこでは医工学連携、産学連携を通じて様々な基礎研究が可能となっています。
TWIns
Tokyo Women's Medical University and Waseda University Joint Institution for Advanced Biomedical Sciences
東京女子医大と早稲田大学による医工融合研究教育拠点
大学院共同先端生命医科学専攻



基礎研究、臨床研究のいずれにおいても大学院修了もしくは一定期間の研究歴の要件を満たせば学位申請が可能です。また、研究留学を希望される際には国内および米国、欧州の各施設に出向が可能です。
主な留学、研修先
- Westchester Medical Center, New York Medical College, NY, USA
- University of Graz, Austria
- Oregon Health & Science University, OR, USA
- Montefiore New Rochelle Hospital, NY, USA
- Krannert Institute of Cardiology, Indiana University, School of Medicine, IN, USA
- National Yang Ming Chiao Tung University, TWN
- Dalton Cardiovascular Center, University of Missouri-Columbia, MO, USA
- Department of Medicine, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA
国際的な活躍の場が広がる
-
海外学会発表
European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ECTES)
The American Association for the Surgery of Trauma (AAST)
World Trauma Congress (WTS) - 英語論文投稿
- 病院・研究施設の見学・研修
- 研究留学
- 臨床留学
教育
大学病院としての重要な責務に教育があります。東京女子医科大学では1学年につき約110名の学生が在籍しており、「至誠と愛」の建学の理念に基づき医学教育、臨床教育が行われています。特に救急医学領域においては国家試験対策のみならず、医師として備えていなければならない臨床能力の基本を身に着けるべく教育を行います。基本的な臨床シミュレーションである、初期診療、救命処置、気管挿管実習に加え、BLS、ACLS、ICLSなどの救急初期診療コースの受講機会を多くの学生に与えるように配慮するとともに、救命救急センターの医師においては指導者として参加していただきます。
大学における教育は医学部、看護学部の学生に対する卒前教育、初期研修医、後期研修医(専攻医)に対する卒後教育に分けられます。専攻医修了後は教育を受ける立場から行う立場に徐々に変遷してゆく過程を経て教官もしくは指導医になります。社会に貢献する女性の医療人を育成するとともに、高い人格を形成する教育を実践します。教育をする立場としての到達目標は、学位取得後のacademic positionの獲得、学生、大学院生、研修医、専攻医、研究者への教育、さらに生涯を教育者としてその役割を担うことにあります。
建学の理念である「至誠と愛」に沿った教育
社会に貢献する女性の医療人を育成

高い人格を形成する教育を行う
到達目標
- 学位取得後のAcademic Position の獲得
- 学部、大学院、研究者、研修医・専攻医教育
- 生涯教育者として貢献
社会貢献
救急医としての社会貢献は1. プレホスピタル、2. 救急隊指導、3. 災害医療、4. 自治体活動、5. 国際交流などがあります。1. においては、病院前、病院内初期診療の各種コースに加え、ドクターカーへの参画があります。2. については、病院内の救急救命士指導、メディカルコントロールが、3. については、日本DMAT、東京DMATでの訓練および派遣、院内トリアージ訓練の開催があります。自治体活動、国際交流については、消防署主催の救急に関する研究会、国際支援、海外での学会発表、誌上発表などがあります。
女性医療者の育成と教育
昨今、女性救急科専攻医は確実に増加しており、働き方改革の推進によるより一層の増加が期待されています。女性医師の救急部門への門戸の拡大がされることによって、働きやすい職場環境を確立し、仕事と生活の両立とsubspecialtyの取得による選択肢の増加が期待されています。その結果、救急医療への興味をいだく機会の提供がされ、時制台のリーダーとなるべき人材の育成につながります。

最後に
東京女子医科大学救命救急センターは以下の目標を方針とし、後期研修医および専攻医の指導、教育を徹底して参ります。
- 女性医師が働きやすく成長できる教室
- 救急医としてのキャリア形成に適した環境
- 臨床・研究・教育にバランスの取れた能力の獲得と職務の遂行
- 学会発表、論文投稿への積極的支援
- サブスペシャリティ、各種資格取得への支援
※見学は救命救急センター医局dem.ag@twmu.ac.jpまで。随時受け付けております。