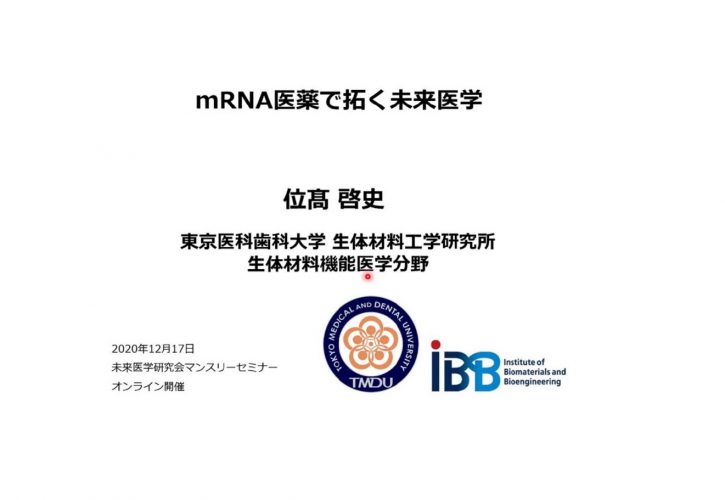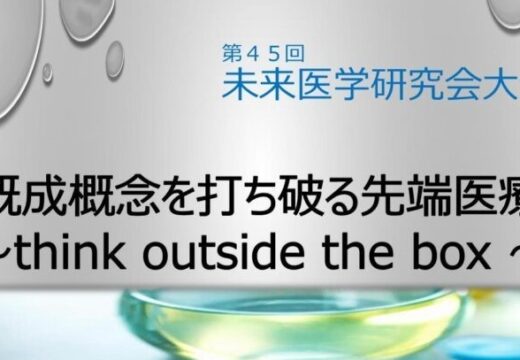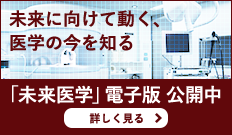「mRNA医薬で拓く未来医学」
先端生命医科学研究所 講師 小林 純
2020年12月18日(木)18時30分から、東京医科歯科大学生体材料工学研究所の位髙啓史教授による未来医学マンスリーセミナーがオンライン開催された。今回の参加者は、1・2・11・12・26・29・30・33・37・45・47・48・50・51・52期及び賛助会員から計45名であった。最近、米ファイザー社と独ビオンテック社、米モデルナ社がメッセンジャーRNA(mRNA)デリバリーを利用してCOVID-19ワクチンを実用化したことが注目された。コロナ禍以前より、mRNA医薬の研究を継続的に進めていた日本で数少ない研究者の一人である位髙教授に、mRNA医薬開発の歴史的経緯と世界的な動向を含めて、ご自身の研究に関するご講演をいただいた。
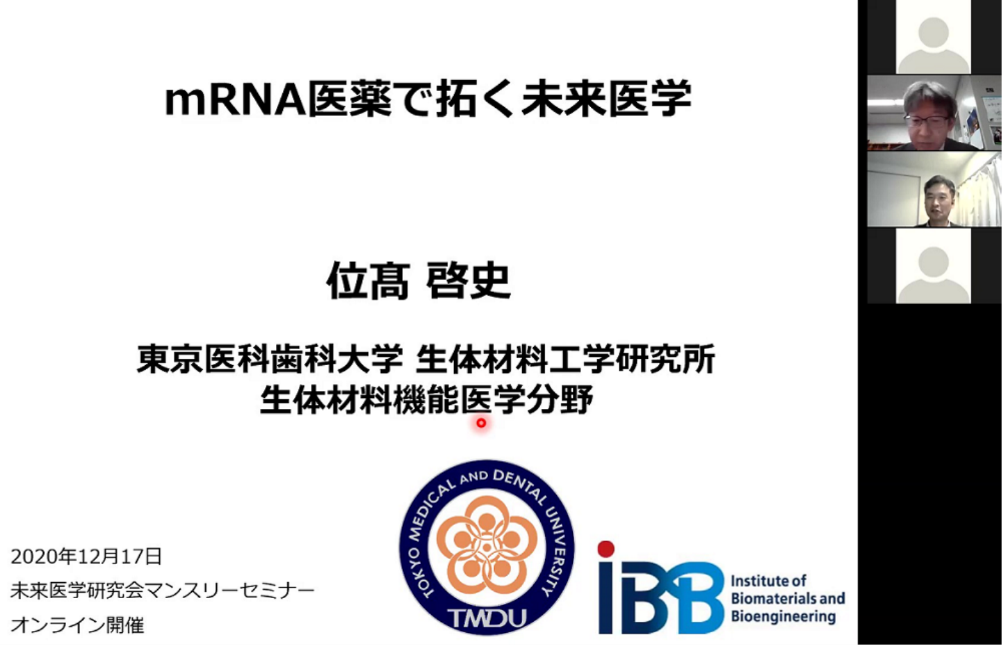
mRNA医薬の特徴は、原理的にどのような細胞にも適用可能で、ゲノムに挿入されるリスクがない安全性である。一方、デメリットはRNA分子が不安定で、免疫反応(具体的には自然免疫)を誘発する。当然、細胞内には無数のRNA分子が存在しており、自己と非自己のRNAをどのように区別しているのかというと、おそらくRNA分子を区別しているのではなく、細胞内で作られたのか、細胞外から取り込まれたかの局在によるものではないかと推察していた。そういった意味で、如何にmRNA分子を細胞内に届けるか、ドラッグデリバリーシステム(DDS)が重要であると指摘していた。また、mRNAを医薬として使えるようになった背景には、mRNA分子に関する基礎研究が進んだことにある。特に、修飾核酸の利用、改良による自然免疫応答の低減にビオンテック社の研究者が寄与していたことを解説していた。
mRNA医薬の社会実装という観点では、現在ワクチン開発と実用化が先行している。mRNAワクチンを含む核酸ベースのワクチンは、ウイルスのスパイクタンパク質など病原体の抗原が同定されれば素早く人工的に合成することができる。また、ワクチン応用に有望な点は、液性免疫だけでなく細胞性免疫を誘導しうることである。特にヨーロッパにおいて、mRNAワクチンは遺伝子治療に分類されないことも含めて、従来のワクチンに比べて数多くの有利な点が実用化を後押ししているということが理解できた。
位髙教授は整形外科医であることもあり、mRNA医薬を用いた関節軟骨や椎間板の治療に取り組んでいる。ナノ医療イノベーションセンターの片岡一則センター長らが開発したポリイオンコンプレックス高分子ミセル(Miyata, K., et al. (2008) J Am Chem Soc 130:16287)に転写因子Runx1のmRNAを内包し、変形性膝関節症(OA)モデル動物の関節に注入すると、軟骨再生を誘導し、OAの進行を抑制することを示した(Aini, H., et al. (2016) Sci Rep 6:18743)。今後、臨床研究に向けた取り組みを開始するとのことであった。また、椎間板変性疾患の治療に関しては、上述と同様の高分子ミセルを椎間板に注入すると、髄核の構造が維持されることを示した(Lin, C.Y., et al. (2019) Mol Ther Nucleic Acids 16:162)。
本講演を通して感じたことは、今般のパンデミックの状況下ではmRNAワクチン応用が注目されがちだが、mRNA医薬の高い安全性とポテンシャルは、将来的には再生治療など新たな領域に適応可能であることだ。しかし、位髙教授が指摘した通り、当該分野における日本のプレーヤーが少ない。今年オンライン開催された8th International mRNA Health Conferenceに参加したのは位髙グループのみだったとのこと。我々アカデミアを含めた積極的な参入が期待される。また、実用化の観点からいうと、mRNA大量合成のためにはRNaseフリーの施設が必要で、大学レベルで設備投資できないのが悩みの種であるとのことだった。本邦におけるmRNA大量合成に特化したファウンドリー設立など、新しいビジネスの可能性があるのではないかと感じた。位髙教授が紹介していたが、mRNA医薬に興味がある方はビオンテック創業者Sahin教授らの総説(Sahin, U., et al., (2014) Nat Rev Drug Discov 13:759)を一読することをお勧めする。