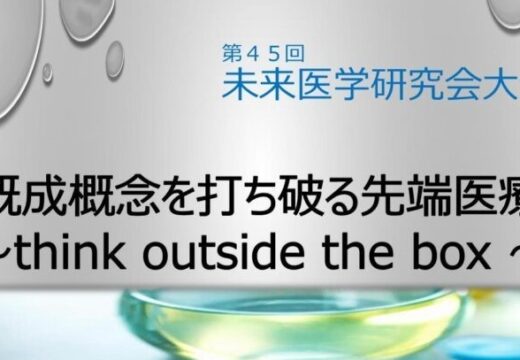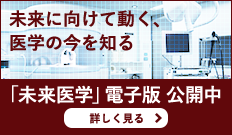「オンライン診療・服薬指導関連」
【開催報告】 未来医学研究会 幹事 関谷佐智子
未来医学研究会、マンスリーセミナーもそろそろ9回目ということで、なかなかしぶとく続いている中、今回は「オンライン診療」がトピックだった。ちなみにこの「オンライン診療」でググッてみるともう何社もヒットする。これは一度学ぶ必要があるだろう、ということで気を引き締めてCOVID-19の第?波が収まりつつある9月10日、本日はオンライン診療サービスの提供会社、MICINのCEO原先生を講師にお招きしてセミナーが始まった。今回の参加者はBMC1,12,25,29,30,37,40,42,43,45,46,48,49,50,51期の修了生、および賛助企業の参加者30名を超えていた。(しかも皆様お時間通りに集合頂き、誠にありがとうございました。)
すでに日経の記事等で先生の経歴等はご存知だと思うが、とても穏やかな、しかしながら、必要不可欠な点をパシっと説明頂けて信頼性とはこういう風に魅せるものなのだなあと感心しながらご講演を拝聴した。なぜ、先生がオンライン診療に取り組んでいるのか、その原動力は医師として感じた「患者となって初めて何故病気になっているのかを知る」という現状をどうにかしたいという志からだ。これは清水会長の人類皆医療人計画?だったか、老若男女関わらず医療知識をつける必要性を訴えていたのと通ずるものがあるような、無いような。ともかく、MICINの取り組みとしてオンライン診療のアプリ管理以外にもデータ活用や臨床開発なども手がけているということだ。オンライン診療は、平成9年遠隔診療通知に始まる。そこから平成27(2015)年の事務連絡において、離島・へき地や慢性疾患の在宅患者は例示でその限りではないということで遠隔診療の取扱が明確化された。2018年に診療報酬が改定され、オンライン診療料等が新設され、本格化が進んでいった。しかしながら、オンライン診療は現実的には2018〜2019年で全体の0.01%未満であり、疾患の限定・初診は対面診療が必要で、報酬が対面より減ずる等々が起因し、伸び悩んでいた。だが、今回のCOVID-19の影響で2020年から疾患の限定がなくなり、主治医の判断で初診からの診療が可能になりぐっと増加が見られたが、一過性な増加ではないかとのことだった。興味深いのは、小児科などで生活環境からの指導(アレルギー等)が可能になったり、性能のよいスマホ画像で喉の診察が対面よりクリアな画像で診察可能だったりとオンライン診療の付加価値が見受けられるという点だった。またMICINは、臨床開発におけるCROとの提携で治験のデジタル化などにも取り組まれており、今後の医薬品・医療機器開発への貢献が期待された。未来、このオンライン診療の方向性としては現状血液検査や触診、打診などができない反面、ウェアラブルデバイスなどが介在することで喘息の聴診や、血圧、心電図の情報が回収可能になったりと、情報の蓄積と診療への応用が加速するのではないかということだった。
 質疑応答では、現状の課題や情報のセキュリティなど興味深いやりとりがあって、修了生の医薬品・医療機器開発に携わる皆様の様々な思惑が感じられる面白い時間であった。(原先生にはこれに懲りず末永くお付き合い頂けると嬉しいです。)今後は「オンライン医療」という新フィールドを構築され、BMCオンライン講義など始まることなどないだろうかと期待が膨らんだ。中国ではすでに5億人が登録しているオンライン診療、日本で全国民オンライン化すると一体どういう世界が拡がるのかおそらく、医師・医療関係者だけでなく、データ管理、デバイス、キャッシュレス、物流等々、想像が及ぶだけでも変化が起こることは間違いないので、今後も持続して考える必要がある内容だとしみじみ思うセミナーだった。
質疑応答では、現状の課題や情報のセキュリティなど興味深いやりとりがあって、修了生の医薬品・医療機器開発に携わる皆様の様々な思惑が感じられる面白い時間であった。(原先生にはこれに懲りず末永くお付き合い頂けると嬉しいです。)今後は「オンライン医療」という新フィールドを構築され、BMCオンライン講義など始まることなどないだろうかと期待が膨らんだ。中国ではすでに5億人が登録しているオンライン診療、日本で全国民オンライン化すると一体どういう世界が拡がるのかおそらく、医師・医療関係者だけでなく、データ管理、デバイス、キャッシュレス、物流等々、想像が及ぶだけでも変化が起こることは間違いないので、今後も持続して考える必要がある内容だとしみじみ思うセミナーだった。