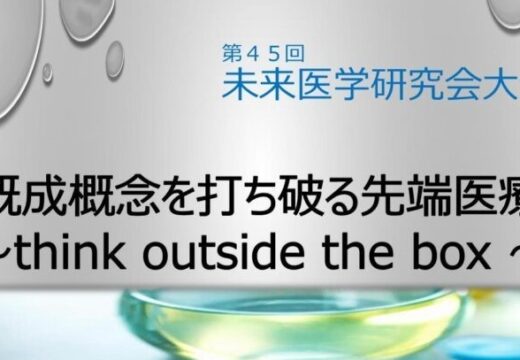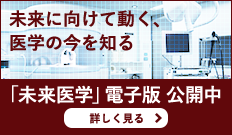24日の夜には天津から北京に高速鉄道で移動した。
北京大学工学院生物医学工程系謝教授および学科長の任教授と会談した。Department of Biomedical Engineering は2005年に設立された。教授5人、associate Prof.4人、修士学生50人、博士課程30人規模。米国のジョージア工科大学とジョイントPhDプログラムを締結している。(ちなみに精華大学はジョンズホプキンス大学と同様なプログラムを進めている)米国での医療工学の第1位はジョンズホプキンスで2位はジョージアテック大学とのこと。任教授からはTWInsとの交流の希望が強かった。岡野先生としては、まずは、学生の人材交流あたりから進めるのがよいと思われるとのコメントであった。
-

北京大学Dept. of Biomedical Engineering,
任学科長と謝教授 -

北京大学構内にある池と塔の風景
北京の中国人民対外友好協会の井副会長からのご招待を受け、程友好交流部部長、張氏と代表団メンバーで会食。日曜日の晩にもかかわらず時間を頂戴したが、代表団としては有意義な交流の場であった。未来医学研究会の訪中目的である日中での先端医療、再生医療を軸とした交流を実現するというビジョンを支持してくださり、3月に引き続き今回9月の訪中時のコンタクト、アレンジ、通訳に至るまで大変お世話になった。日中文化交流協会と中国人民対外友好協会のサポートがなければ今回の訪中も実現はしなかったと思う。
北京では、精華大学第1付属病院の呉院長を訪問した。3月に続く2回目の訪問である。呉院長は心臓外科では高名な先生。
岡野先生より、細胞シートの説明に続き、アジア主導の先端医療についてのビジョンを伝えた。すなわち、GMPなど欧米方式だと何百億円も費用がかかる。これだとアジアの企業は手が出せない。コストを安く、ひとりでも多くの人を救える医療を実現したい。これをアジアから発信する。医療デバイスではアジアが世界をリードしたい。細胞シート治療は薬事法に縛られずに進めたい。サイエンスに基づくことが大事で、国際的なコラボが必要である。
呉先生より、協力していきたい。治らない患者を治すのは素晴らしい。中国でも細胞シート治療が適用される患者は数多くいるので、細胞シートを使っていきたいと思う。
→ 細胞シートをアジアでちゃんと使っていけるようにしたい。日中で協力して欧米の追従を許さないような新しい医療を実現したい。というところでまとまった。
-

精華大学第1病院訪問 -

手術室見学(装置は日本並みの充実)
26日の夜に最後の訪問地上海に夕刻到着。上海交通大学国際合作与交流処主任 許准教授と情報交換。中国では天津大学、上海交通大学の順で歴史がある。交通大学の交通はコミュニケーションの意。医学部の学生数は上海交通大は350人/一学年、フタン大学も350人/一学年、同済大も同様。一学年1000人を超える医師が上海からだけでも毎年生まれている。
-
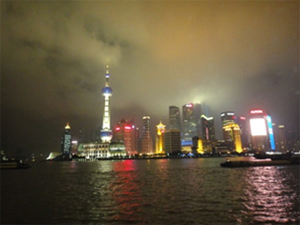
上海 浦東の夜景、節電は何処のことか? -

上海の最初の訪問病院は上海第9人民病院。曹副院長を3月に引き続き訪問。曹副院長は中国のTissue Engineering分野でトップクラス。中国では組織工学、幹細胞治療の認可が極めて厳しくなっている。現在は認可は皮膚くらいしか組織工学分野ではとれていない。GMPラボが必要であり、病院内でのセットアップは難しく、別の場所に現在建設中。特に安全性を検査することが重要。上海FDA(SFDA)ではフレキシブルなところもあるので、安全と認めてもらうことが必要と考えているとのこと。クリニカルトライアルは行うことができるので、まずは小さくてもよいから成功例を作って政府を巻き込んでいくのがよいとのこと。
岡野先生からは欧州では30カ国がひとつのregulationに基づいている。若い人を未来に向けて教育していかないとならない。気を付けなければならないのは、米国で学び、その手法が最高だと思って、そのまま中国に帰国してからも高価な診断装置、治療装置、薬を輸入し、治療を続ける。既に天津、北京での視察した病院では日本並みの手術室設備、検査装置が導入されていることからもこの流れが始まっていると思う。しかし、10年、20年後にはどうするのか?日本のように医療費ばかり上がってしまい、多くの患者を治すことにはならない。中国は人口も多く、多くの患者を治すために医療をどうしたらよいかを真剣に取り組む必要がある。この病院ともアイデアを交換して、小さなスケールから始めるのがよいだろう。安全性と効率をきちんと見極めて、問題があればすぐストップしなければならないのは勿論だ。
上海では新しい技術の認可について、ひとつの病院でしか治療ができない制限があるが、それであれば可能である。
まずは、眼科患者が多く、角膜移植ドナーも少ないことから角膜の細胞シート治療を行う方向で検討を進める。データを見せて優れていることを示すことを日中で協力して行う。2013年からはフランスで治療が始まるので上海でも1.5年すればスタートすることができるだろう。欧州のシステムをモデルとしてアジアに適用していくことも考えたい。中国では200例程度のデータがスタートから2年後には揃うだろう。そのためにTWInsから技術移管を行う。SFDAもデータを見て納得できるレベルが達成できると曹副院長も考えている。
→いずれにしろ、議論を続ける。